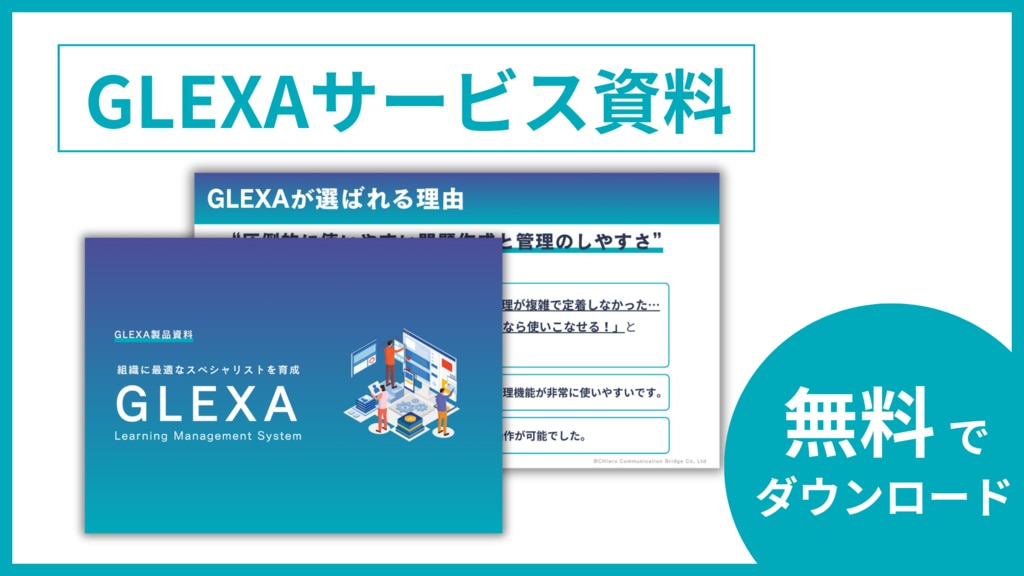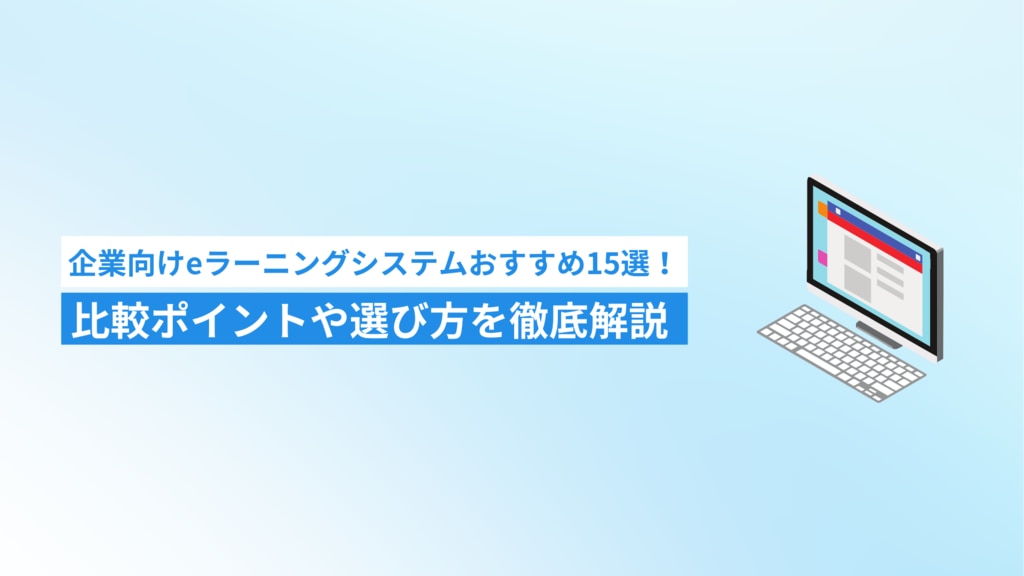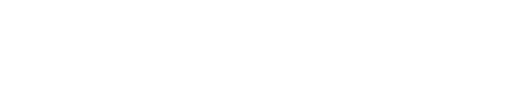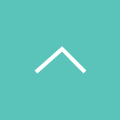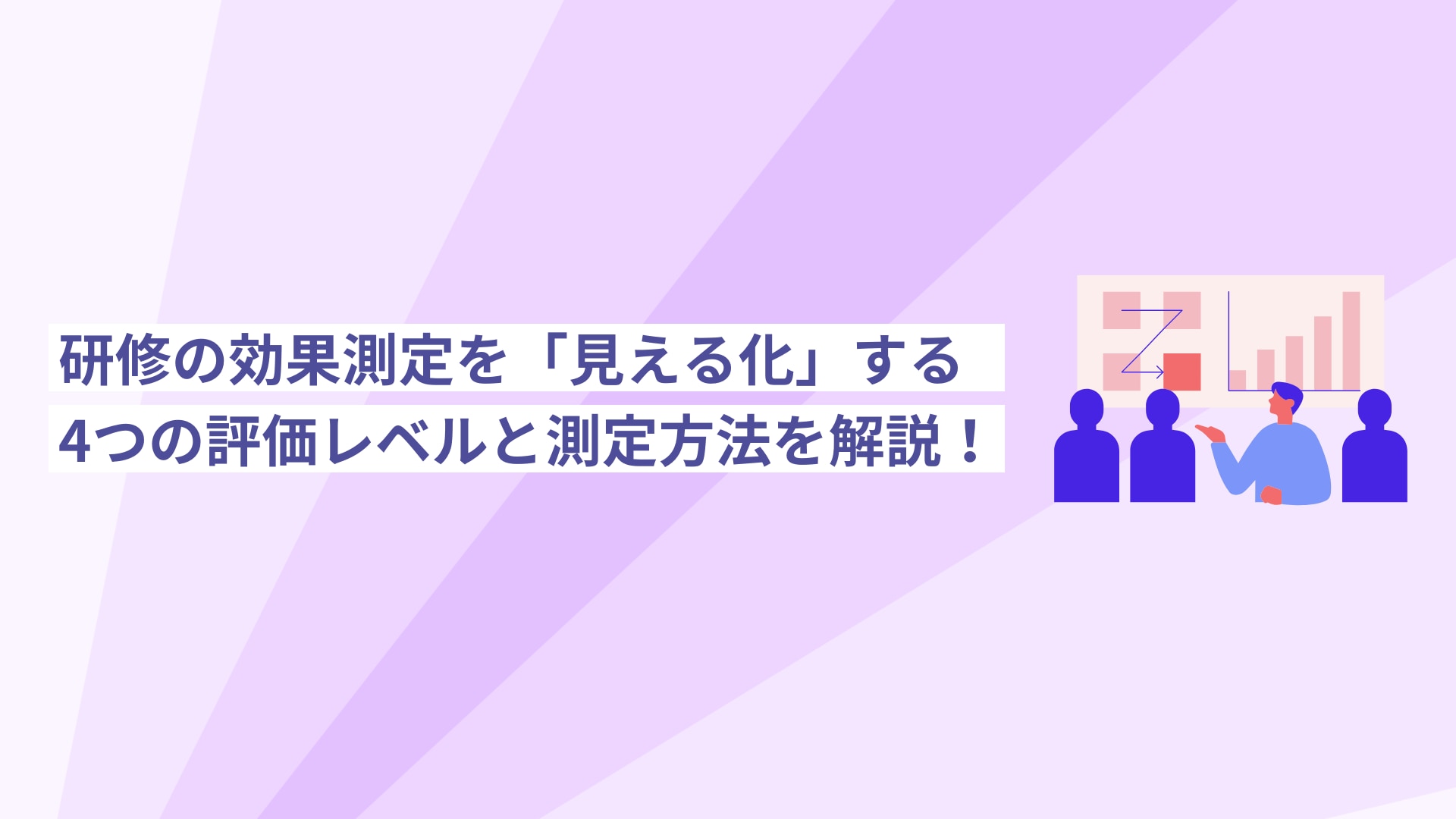
研修の効果測定を「見える化」する4つの評価レベルと測定方法を解説!
社内研修などの人材育成は、従業員のスキル向上や組織全体の成長に必要不可欠です。しかし、研修を実施しただけで終わってしまっては、効果が十分に発揮されているか、期待する成果が得られているかを確認できません。そこで重要となるのが「研修効果測定」です。
本記事では、研修効果測定の目的や必要性、代表的な評価フレームワークであるカークパトリックモデル、具体的な測定方法について詳しく解説します。
目次[非表示]
▼おすすめの関連記事
「今時の人材はどんな感じ?人材育成のトレンド解説!」
「社内教育プログラムの企画手順と成功の秘訣」
「組織力アップ!社員のスキルを「見える化」する方法」
研修効果測定とは?
研修効果測定は、社内で実施した研修が、どのような影響を与えたのかを客観的に評価し、より効果的な人材育成へ改善するために必要なプロセスです。ここでは、なぜ研修効果測定が必要なのか、理由や役割などを解説します。
研修効果測定の目的と必要な理由
研修効果測定が必要な理由は多岐にわたります。主な目的は、社内研修の評価を客観的に行うことですが、行動変容や業績向上といった結果も評価の対象となります。
研修効果測定を行う具体的な目的には、次のようなものがあります。
- 研修効果を明確にする:研修によって受講者の知識・スキルがどれくらい上昇したかを可視化する
- 研修後のフォローアップにつなげる:効果測定の結果から受講者の理解度や習熟度を把握し、一人ひとりの課題に応じた個別フォローや再研修を実施できる
- 研修プログラムの継続的な改善:研修内容や運用方法の課題を特定し、次回以降の研修に反映することで、質の高い研修を構築できる
- 研修そのものを見直す:研修には多くの費用・時間がかかるため、費用対効果が低い場合は実施自体を見直すきっかけとなる
下記の記事では、新時代の人材育成について詳しく解説しています。社内研修の効率化などへ積極的に取り組んでいる方は、下記の記事も参考にしてください。
▼おすすめの関連記事
オンライン化が進む中での効果測定の役割
近年、働き方改革やコロナ禍の影響で、研修のオンライン化が急速に進んでいます。オンライン研修は場所や時間の制約が少なく、受講者の負担軽減やコスト削減など多くのメリットがありますが、一方で次のような課題が発生しています。
- 受講者の集中度や参加意欲の低下
- グループワークやディスカッションの実施が困難
- 受講状況や成果がリアルタイムで把握しづらい
- 対面研修に比べて参加者の反応が見えにくい
オンライン研修では、受講者のログイン履歴やテスト結果などの情報を収集しやすく、従来の研修よりも効果測定がしやすい状況になっています。そのため、受講者一人ひとりの理解度や行動変容を「見える化」することで、上記のようなオンライン研修の課題を克服でき、より効果の高い人材育成を行えるようになります。
研修効果測定の評価方法「カークパトリックモデル」とは
世界中の企業や教育機関で、研修効果測定として採用されている方法に「カークパトリックモデル」という評価方法があります。カークパトリックモデルは、経営学者ドナルド・カークパトリックが、1959年に提唱し1975年ごろから広く活用され始めた、研修・教育の効果を評価するフレームワークです。ここでは、研修効果測定の基本でもあるカークパトリックモデルについて、レベルごとに特徴や具体例を解説します。
レベル1:リアクション(反応)
カークパトリックモデルにおけるレベル1の評価方法は、「リアクション(反応)」を評価することです。実施した研修に対して、受講者はどのような反応・感想を持ったのかを測定します。具体的には、次のような項目で測定します。
- 「研修に期待した内容だったか」などの質問を含めたアンケート
- リアルタイム投票の結果やチャットの反応
- 満足度を5段階評価などの具体的な数値による評価アンケート
- 自由記述で受講者の感想や意見を広く収集
上記のように、レベル1の効果測定では、アンケートなどを使った評価方法で測定することが多いです。一方で、満足度が高くても「楽しかった」「わかりやすかった」など簡単な感想だけで終わってしまい、研修に対する具体的な評価や実際の学習結果の測定につながらないケースもあります。
また、研修後のアンケートを何度も行っていると形骸化しやすく、毎回決まった回答しか得られないことも多いです。そのため、レベル1の評価が高かったとしても、研修が効果的だったとは判断できません。
レベル2:ラーニング(学習)
レベル2で評価するものは「ラーニング(学習)」、つまり受講者が研修を通じて「どれだけ知識やスキルを習得したか」を測定します。受講者一人ひとりに対して、研修で学んだ内容を理解し、知識として定着しているかを確認します。レベル2の効果測定では、次のような測定方法を行うことが多いです。
- 研修前後の理解度テスト(選択式・記述式)
- ケーススタディやロールプレイ
- グループワークの発表内容
- 実技試験やレポート
レベル2の効果測定でテストを行う場合、単に研修内容を問うものにしてしまうと記憶の確認となり、知識の定着度や理解度まで測定できないことがあります。そのため、テストの設問は、「現場での実践を想定した内容」にし、応用力や問題解決力を評価できる内容を考えることが大切です。
レベル3:ビヘイビア(行動)
レベル3の測定項目は「ビヘイビア(行動)」です。受講者が研修で学んだことを、実際の業務現場でどの程度実践できているかを評価します。そのため、研修直後の確認テストだけでなく、1か月後や3か月後など、一定期間ごとに、現場での行動変化を観察・調査することが大切です。具体的には、次のような手法・方法を用いて受講者の行動をチェックします。
- 上司や同僚による行動観察・評価シート
- 受講者自身による自己評価シート・行動記録の提出
- 複数の関係者からの評価・フィードバック
レベル3の効果測定では、基本的に人による評価が中心となるため、担当者によって評価基準がバラバラになるなどの課題が生じることがあります。そのため、複数の担当者の意見を参考にしたり、評価基準を標準化したりすることが必要です。
レベル4:リザルツ(結果)
レベル4の評価項目は「リザルツ(結果)」、すなわち「組織全体の業績や生産性への影響」の評価です。受講者が研修を通して学んだことを活かして行動した結果、業績や生産性が向上した、コスト削減につながったなど、ビジネス上の具体的な成果に結びついているかを確認します。具体的には、次のようにレベル4の評価を行います。
- 研修前後の業績データ比較(売上、利益、成約率など)
- 顧客アンケートによる満足度・クレーム件数の推移
- 業務プロセスの効率化度合い(作業時間の短縮、ミスの増減など)
- 研修受講者と非受講者の業績比較
レベル4の評価で使用するデータは、単に研修結果だけが反映されたものではないことに注意が必要です。景気変動や組織の再編など、研修とは関係のないことも業績に影響します。そのため、研修との因果関係だけを特定するのは難しいということを理解したうえで、評価することが大切です。
社内研修でカークパトリックモデルを活用するポイント
カークパトリックモデルは4つのレベルに分かれており、レベルごとに効果測定の方法も異なります。そこで、社内研修の効果測定にカークパトリックモデルを使う場合は、次のポイントを意識して測定を行いましょう。
- 研修の目的やゴールを明確にし、どのレベルまで評価するかを事前に決める
- 各レベルに応じた具体的な評価指標・測定方法を考える
- 測定結果を現場や経営層と共有し、課題や成功要因の分析を行う
- 研修の種類や目的に応じて、重要度の高いレベルの効果測定に注力する
- 測定可能な目標を設定する
- 評価のタイミングを設定する(レベル1、2は研修直後から数日以内、レベル3は数か月後、レベル4は半年から1年後が目安)
例えば、新入社員研修ではレベル1~2を重視、管理職研修ではレベル3~4を重視するといったように、研修内容や対象を明確化すると、より効果的な効果測定が可能になります。さらに、評価結果を全社で共有し、他部署の成功事例を横展開すると、効率よく会社全体の人材育成力を強化できます。
下記の記事では、社内研修を実施するときに必要なプログラムの企画作成について詳しく解説しています。効果的な社内研修を行いたい場合は、ぜひ参考にしてください。
▼おすすめの関連記事
研修効果測定の主な方法
研修の効果測定方法には、定量評価や定性評価といったさまざまな方法があり、方法によって得意・不得意があります。カークパトリックモデルを十分に活かすために、ここでは効果測定の代表的な方法を紹介します。
定量評価
定量評価は、「数値」で表せるデータを用いて研修効果を客観的に評価する手法です。比較や分析がしやすいというメリットがあるため、初めて効果測定を実施する場合でも比較的行いやすい方法です。定量評価の具体的な方法には、次のようなものがあります。
- テスト・クイズ:研修前後に実施し、結果を比較することで研修内容の理解度や知識の定着度を確認できる
- アンケート:研修の満足度や理解度などを5段階評価で測定でき、受講者の反応を数値データとして収集・分析を行える
- KPI・業績データ:売上や利益、生産個数などのKPIを用いて、研修前後や受講者と非受講者のデータを比較・分析することで、研修の影響を客観的に評価する
- ROI分析:研修にかかった費用に対する利益を測定し、研修に対する費用対効果を数値化し分析する
定性評価
定性評価は、受講者の意見や行動、意識の変化といった、数値化しにくい要素を評価する方法です。受講者の意識変化や現場での実践度、研修の質的な側面を深く理解するために有効です。定性評価の具体的な方法には、次のようなものがあります。
- アンケート(自由記述項目):受講者の具体的な感想や意見を収集することで、研修内容や運用に関する質的なフィードバックを得る
- ヒアリング・インタビュー:受講者本人や周囲の関係者(上司、同僚など)に直接話を聞き、研修の学びや実務での活用状況、意識の変化などを評価する
- 行動観察:研修で学んだ内容が実際の業務行動に反映されているかを、上司や同僚などが観察し評価する
- レポート・論文:受講者が研修内容を整理し、自身の言葉でまとめることで、理解度や思考の深化を確認する
オンライン研修の効果測定方法
オンライン研修の効果測定方法でも、定量評価と定性評価の両方が効果的です。一方で、LMS(学習管理システム)をはじめとした、各種デジタルツールを活用することで、従来の研修よりも受講者の受講状況や成果をリアルタイムで可視化できるという強みがあります。
オンライン研修の効果測定で使われる方法には、次のようなものがあります。
- LMSの活用:受講履歴や学習進捗状況、テスト結果などを一元管理し、自動集計することで、効率よくオンライン研修の効果測定を効率化できる
- オンラインテスト・クイズ:オンライン上の理解度テストと、自動採点・集計機能を組み合わせて活用することで迅速に学習成果を測定できる
- オンラインアンケート:研修後の満足度やフィードバックをLMSなどの機能を使って収集し、自動集計やグラフ化することで簡単に分析できる環境を整えられる
- 行動ログ分析:受講者のログイン頻度やコンテンツの視聴時間、テストへの再挑戦回数といった行動ログを分析し、学習への取り組み姿勢や興味関心などを客観的に評価する
研修効果の「見える化」事例紹介
研修効果を「見える化」することで、成果を研修関係者内で共有しやすくなり、改善に向けた具体的な議論が進みます。そこで、研修効果の「見える化」の具体例を紹介します。
- 受講前後のテスト比較
研修開始前と終了後に同じテストを実施し、平均点や正答率の変化をグラフ化します。この手法によって、知識や理解度の伸び率を可視化でき、苦手分野の特定やフォローアップ対象者の抽出などに活かしている企業が増えています。
活用事例:新入社員研修の前後に業界知識テストを行い、前後の点数を比較することで社員の理解度や研修の効果を把握する。
- 行動変容のチェックリストの採用
「挨拶の徹底」「報告・連絡・相談の頻度」など具体的な行動項目をリスト化し、上司や同僚が一定期間ごとにチェックします。研修後の行動がどのように変化しているかを可視化することで、研修の実務への定着度を確認します。
活用事例:管理職研修後に、部下へのフィードバック面談の実施回数の増減、具体的な行動を示せているかなどを継続して評価する。
- 業績指標のグラフ化
研修前後の「売上」「成約件数」「顧客満足度」といったKPIを時系列でグラフ化し、研修実施月からどのように変化しているかを継続的に評価します。そして、一定期間ごとに成果の波及効果や持続性を分析し、次回の研修の改善に活かすことで、より実践的な研修ができる環境を整えます。
活用事例:研修後のデータを見える化し、PDCAサイクルに取り入れることで、研修効果の測定・改善を図り、研修1回あたりの費用対効果を向上させる。
- デジタルツールの活用
LMSやBIツールといったデジタルツールを使い、受講状況や成果指標をリアルタイムで「見える化」する企業も増えています。経営層や現場マネージャーが、いつでも社員の進捗・成果を把握でき、能力に合った仕事の割り振りやフォローアップの実施に活用されています。
活用事例:タブレット端末を用いたアンケートやテストで、効率的に受講者の状況を収集し、管理者や担当者がいつでもデータを閲覧できるようにする。
下記の記事では、同じ「見える化」でも、社員一人ひとりのスキルを見える化する方法やメリットについて解説しています。人材育成のその先を見据えた内容になっているので、以下の記事も合わせてチェックしてみてください。
▼おすすめの関連記事
効果測定結果を活かした研修プログラムの改善方法
研修効果測定で重要なのは、単に効果を測定するだけで終わるのではなく、結果をもとに研修プログラムを改善することです。ここでは、研修効果測定の結果を、次回以降の研修プログラムや運用方法の改善につなげるための方法について解説します。
効果測定結果の分析・フィードバック
効果測定結果を次の研修に活かすには、収集した意見やデータの分析、教育効果の検証を行い、受講者や関係者へフィードバックすることが重要です。
効果測定結果の分析では、定量データ(テスト結果やKPIなど)と定性データ(受講者の声や行動観察など)を組み合わせて分析します。例えば、研修後の満足度は高評価でも、期待するような結果が出ていなければ、研修の効果は低いと分析できます。
2つの評価データを用いて、伸びている点や課題点、想定外の成果などを抽出することで、今回の研修の効果をより詳しく分析しましょう。
結果の分析を終えたら、分析結果を受講者や関係者へフィードバックします。具体的には、対象者ごとに次のようなフィードバックを行います。
- 受講者:データから分かる本人の強みや弱み、今後の課題など
- 上司や現場マネージャー:部下の成長ポイントや追加フォローの必要性など
- 経営層:費用対効果や組織全体への波及効果など
伝える相手に合わせて「どの部分を、どのように改善すべきか」を具体的に伝え、受講者一人ひとりの成長をサポートしましょう。
改善サイクル(PDCA)への組み込み方
効果測定結果を効果的に活用するためには、研修プログラムの改善サイクル(PDCA)に組み込み、継続的なブラッシュアップを行うのが効率的です。そこで、次のようなことを意識して、それぞれのサイクルに合わせて効果測定結果を活用してみましょう。
- Plan(計画)
効果測定の結果をもとに、次回研修の目標や内容、評価指標を再設計します。特に、前回の研修で判明した課題や改善点をもとに、測定可能な目標を改めて設定することが大切です。 - Do(実行)
改善点を反映した研修プログラムを実施します。計画段階で新しく設けた要素や改善策をきちんと実現するよう、研修を実施しましょう。 - Check(評価)
再度効果測定を実施し、改善の成果や新たな課題を評価します。前々回や前回の結果と比較して、どのような改善が見られたか、新たな課題が発生していないかを詳細に分析します。 - Act(改善)
教育効果の評価・分析結果に基づいて、さらに効果を高めるための改善策・確認方法を検討します。そして、次の計画策定時に反映させることを徹底することで、研修の質と成果を向上させます。
下記の記事では、社内研修が形骸化しないよう、コンテンツの質向上に効果的な内容をまとめています。より良い社内研修を行うためには参考になる内容ばかりなので、ぜひ以下の記事も活用してください。
▼おすすめの関連記事
研修効果測定のよくある失敗
研修効果測定は重要である一方、実際に行うには専門的な知識や技術も必要なこともあり、失敗してしまうケースも少なくありません。効果測定でよくある失敗には、次のようなものがあります。
- 測定基準が曖昧:何を測定するべきか、どのような基準で評価するかが曖昧なまま測定を開始したため、信頼性の低い結果が出てしまった
- 他部署との連携不足:人事部門や研修担当者だけで測定を完結したため、受講者の行動変容や業績への波及効果が把握できなかった
- アンケートだけ実施:受講直後のアンケート(満足度調査)だけで満足し、学習定着度や行動変容などを測定しなかった
- 測定だけ実施:効果測定自体が目的となり、研修内容の改善や個別フィードバックなどを行わなかった
- データの活用不足:必要以上のデータを収集したことで、分析や改善に時間がかかり、十分に活かせなかった
研修効果測定を失敗しないためのポイント
研修効果測定の必要性は高まっている一方で、その成果を最大限に引き出せなければ、費用対効果が薄く、測定を行う意味がなくなってしまいます。ここでは、研修効果測定を失敗しないための対策・ポイントを解説します。
研修効果測定を成功させるコツ
研修効果測定に多い失敗例を参考に、専門知識や技術がなくても効果測定を成功させるコツには、次のようなものがあります。
- 目的・評価指標の明確化:研修を企画する段階から、カークパトリックモデルを活用して、研修を行う目的、効果測定の評価レベル、具体的な測定指標を明確に設定する
- 各関係者と協力する:研修の目的や効果測定の必要性を、現場の管理職や経営層に説明して協力を仰ぎ、評価・改善のプロセスを共有する
- 測定方法のバランスを重視する:測定方法が偏らないよう、定量評価と定性評価をバランス良く組み合わせ、多角的に測定できるようにする
- 測定結果を活用する:改善サイクル(PDCA)への組み込みや定期的な振り返りなど、測定だけで終わらせない
初めて効果測定を行うときは、まずこの4つのポイントを意識して研修と効果測定に臨みましょう。
効果測定を形骸化させないための工夫
効果測定を何度も行っていると、工数の多さや複雑さから、次第に最初の頃よりも熱意が下がり、形骸化することがあります。形骸化した効果測定は「やっただけ」になり、人材育成にプラスにはなりません。そこで、次のような工夫を行い、効果測定が形骸化しないように取り組みましょう。
- 評価観点を絞る:すべての研修であらゆる項目を測定しようとすると、膨大な手間とコストがかかるため、最も重要な指標や現場に直結する行動に絞って評価する
- 測定方法を効率化する:デジタルツールを活用し、データ収集・集計・分析の一部を自動化することで、効果測定にかかる負担を軽減する
- データの「見える化」:研修成果を把握しやすくすることで、現場のモチベーションや協力を高める
- 改善に関する仕組みを作る:定期的なレビュー会議の開催、改善提案の募集など、測定結果を活かす仕組みを作ることで、関係者のモチベーションを維持する
効果測定の形骸化を防ぎ、常に研修内容の改善に取り組んでいくことは、結果的に会社の売上アップなどにつながります。担当者や関係者の負担を削減しつつ、うまくモチベーションを保つよう工夫していき、質の高い人材育成環境を整えましょう。
オンライン研修の効果測定について
コロナ禍以降、オンライン研修は急速に普及し、現在では企業の人材育成の主流となりつつあります。しかし、オンラインならではの課題も多く、従来の効果測定方法では対応が難しいこともあります。ここでは、オンライン研修の効果測定について、必要性や測定方法、ツールの選び方などを解説します。
オンライン研修こそ効果測定が必要な理由
オンライン研修は、受講者にとってメリットが多い一方、研修効果に疑問を持つ担当者も少なくないことから、従来の研修よりも効果測定の必要性が高いとされています。オンライン研修で効果測定が必要な理由は、主に次の2つです。
- 受講者のリアクションが見えにくい:受講者が本当に理解・納得しているか、集中しているかが把握しづらく、カメラがオフになっているとリアクションが見えない
- 「サボり」が発生しやすい:オンライン研修は受講者の自己管理やモチベーションに依存するため、進捗遅延や形だけの受講が発生しやすい
従来の研修と違って、オンライン研修は業務として受けるという感覚が薄くなり、真剣に取り組む意識が低下する傾向があります。そのため、ログイン状況やテストの点数など、各種データを用いた客観的な効果測定が不可欠になっているのです。
下記の記事では、オンライン研修について幅広い角度から解説しています。利便性の高いオンライン研修をより効果的に活用するためには、参考になる情報が網羅されているので、合わせてチェックしてください。
▼おすすめの関連記事
「現場が学ばないのは誰の責任?~eラーニングの落し穴と育成設計での対応ポイント~」
オンライン研修の効果測定をサポートするツール
オンライン研修の効果測定を効率的に行うためには、デジタルツールの活用が欠かせません。そこで、さまざまな企業で採用されている主な効果測定のデジタルツールを紹介します。
- LMS(学習管理システム):受講履歴、進捗状況、テスト結果、課題提出などを一元管理し、受講者ごとのデータをリアルタイムで可視化する、オンライン研修の効果測定において中心となるツール
- オンラインテスト・クイズツール:事前・事後テストの採点や理解度チェックのフィードバックを自動化することで、迅速な効果測定が可能
- アンケートツール:受講後アンケートや定期的なフォローアップ調査を効率的に実施でき、回答の自動集計やグラフ化機能により、分析の手間も軽減できる
- 行動ログ分析ツール:研修動画の視聴時間やテストの受験回数などを可視化でき、学習へのエンゲージメントや難しいと感じている点などを分析できる
オンライン研修の効果測定では、基本的にLMSを中心に必要な機能・ツールを組み合わせて使用します。そのため、まずは核となるLMSの選定に注力するとよいでしょう。
導入するツールの選定ポイント
オンライン研修の効果測定で使用するツールを選ぶ際に重要なのは、自社の研修目的や運用体制に合ったものを選ぶことです。そこで、次のようなポイントを意識して、自社で扱いやすいツールを見つけましょう。
- 操作性:受講者・管理者のどちらも直感的に使えるか、最低限のマニュアルでも運用できるか
- データ集計・分析機能:測定に必要なデータを簡単に抽出・見える化できるか、個人・グループ・全体など対象に応じた分析が可能か
- 既存システムとの連携:社内の人事システムや評価システムとデータ連携できるか
- コスト:導入・運用コストが予算内に収まるか、自社の利用規模に適したコストパフォーマンスか
- サポート体制:トラブル時のサポートや運用ノウハウの提供が充実しているか、導入時の研修を実施しているか
- セキュリティ・個人情報保護:データ暗号化、ユーザー認証、アクセス制限などのセキュリティ機能が充実しているか
デジタルツールを導入する際は、どうしても機能性を追求してしまい、高性能なツールを選ぶことが多いです。しかし、性能を十分に活用しきれず、持て余してしまうこともあるため、必要十分なツールを選ぶようにしましょう。
まとめ
研修効果測定は、企業や組織の人材育成を進化させるための成長エンジンとなるものです。手間や時間がかかったり、難しいと感じることも多いですが、その分研修の質を高め、社員の成長促進や会社全体の生産性向上といった効果をもたらします。
そのため、カークパトリックモデルをベースにした評価手法を活用しつつ、定量・定性データをバランスよく組み合わせながら、研修効果測定にチャレンジしてみてください。そして、測定して終わりにするのではなく、測定結果を次の成長につなげることを意識して、継続的に測定と改善を行い、質の高い人材育成環境を作り上げましょう。
▼おすすめの関連記事
「今時の人材はどんな感じ?人材育成のトレンド解説!」
「社内教育プログラムの企画手順と成功の秘訣」
「組織力アップ!社員のスキルを「見える化」する方法」