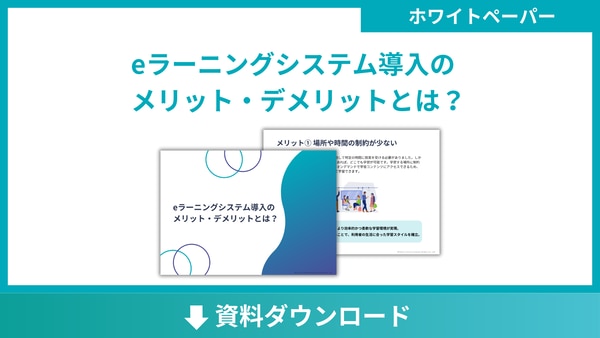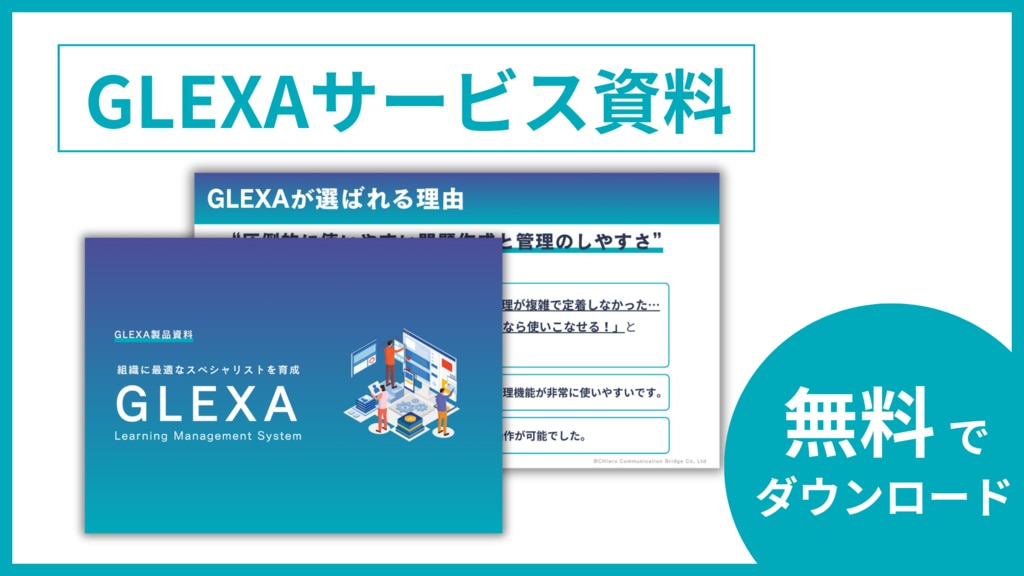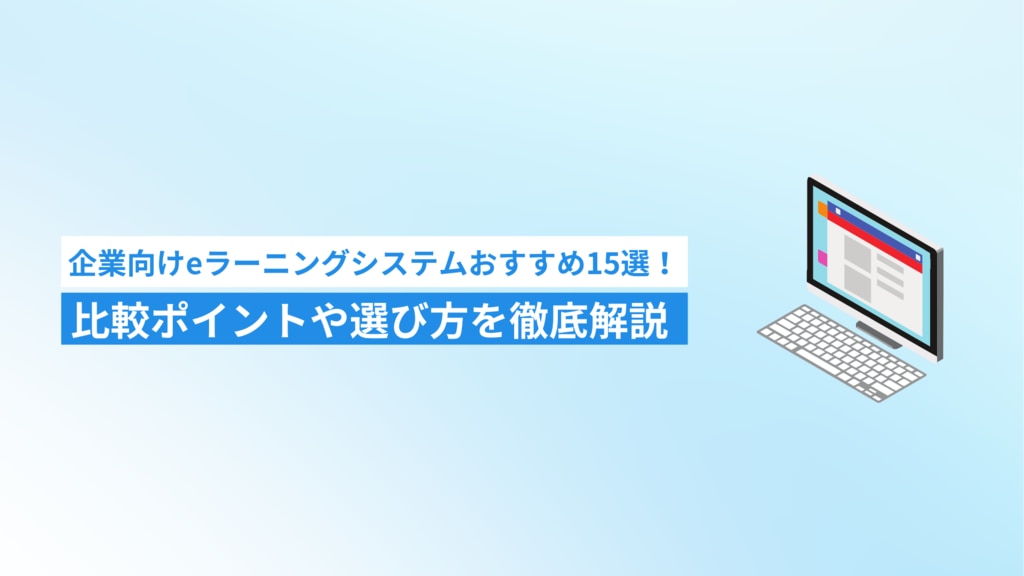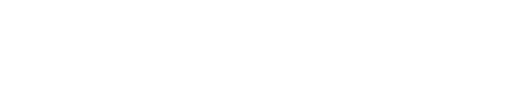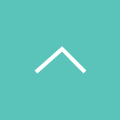eラーニングのデメリットとは?企業側の導入メリットや学習効果を高める方法を徹底解説
現代の人材育成において、eラーニングは時間や場所の制約を受けない効率的な学習手段として注目を集めています。しかし、導入には数多くのメリットがある一方で、避けて通れないデメリットや課題も存在するのが現実です。
単にシステムを導入するだけでは、期待した成果は得られません。課題を事前に把握し、適切な対策を講じることこそが、eラーニングの真の効果を最大化する鍵となります。
本記事では、eラーニングを正しく活用するために押さえておくべき主要な4つのデメリットについて、実践的な対策とともに詳しく解説します。
目次[非表示]
▼おすすめの関連記事
「社内研修の効果を高めるLMS(学習管理システム)とは?機能と活用事例を紹介」
「企業のためのLMS活用術!5つのメリットを公開」
「企業の未来に直結!若手社員を成長させるための育成術」
eラーニング導入前に知るべき4つのデメリットと問題点
eラーニングの導入には多くのメリットがある一方で、避けられないデメリットも存在します。そのため、デメリットを把握し対策をしないと、せっかく導入しても効果がないと感じてしまいます。そこで、eラーニングを正しく使いこなすためにも、主な4つのデメリットについて解説します。
デメリット①:システム・技術的な課題
eラーニングはインターネットを基盤とした学習システムであるため、技術的な課題が学習の成否を大きく左右します。この技術への依存性こそが、重要なデメリットの1つといえるでしょう。
接続不良やシステム障害による学習機会の損失リスク
eラーニングにおいて、インターネット接続の不安定さは大きな課題です。特に、リアルタイムで行われるオンライン授業では、接続が途切れ途切れになることで受講の継続が困難になるケースが頻発しています。
ネットワーク障害が発生すると、授業が途中で中断されたり、学習進捗が正しく記録されずに再受講が必要になったりと、学習者にとって大きなストレスとなります。特に、通信速度が遅い地域やインフラが整っていない地域では、eラーニングのコンテンツを全て利用できず、学習機会に大きな差が生じることもあります。
デバイスやネットワーク環境による学習格差の発生
eラーニングの学習環境は、学習者のデバイスに大きく依存しているため、ハードウェアやソフトウェアの問題が発生すると、学習が中断される可能性があります。さらに、学習者が使用するデバイスのスペックが不足している場合、スムーズな学習が難しくなることもあります。
また、デバイスの画面サイズや解像度の違いによって資料の視認性が悪化したり、特定のデバイスでしか利用できない機能があったりと、デジタル環境の差異が直接的に学習格差を生み出してしまいます。
セキュリティリスクと情報漏洩対策が必須
eラーニングシステムは、社員の個人情報、試験結果、研修内容といった機密性の高いデータを大量に取り扱います。セキュリティ対策が不十分な状態では、個人情報の漏洩やコンテンツの不正使用など、企業にとって致命的な事故につながる恐れがあります。
不正アクセスやマルウェア対策、データ暗号化、アクセス権限の厳格な管理、ログ監視といった多層的なセキュリティ対策の徹底が不可欠です。加えて、セキュリティ事故が発生した際の初動対応マニュアルの整備や、社員への情報リテラシー教育も重要な要素となります。
万が一情報漏洩などの事故が発生した場合、企業ブランドや社会的信頼に深刻なダメージを与えることになります。そのため、堅牢なセキュリティ体制を確保したシステムの構築と継続的な運用が求められます。
デメリット②:eラーニング導入コスト・リソースの課題
eラーニングは長期的な視点では研修コストの削減効果が期待できますが、導入時には相当な初期投資と継続的なリソース投入が必要となります。高品質な学習環境を整備しようとすると、予想以上のコストと人的リソースが必要になるケースが少なくありません。
初期導入コストと運用コストの見込み違いによる失敗
eラーニングシステムの導入費用は、選択する形態によって大きな差があります。クラウド型であれば初期費用5~20万円程度で始められる一方、オンプレミス型では100万円を超える投資が必要になることも珍しくありません。
特に注意すべきは、導入時に費用の全体像が見えないことです。ユーザー数の増加に伴う課金、システムのカスタマイズ費用、コンテンツの定期的な更新や保守といったランニングコストにより、最終的に当初の想定費用を大幅に上回る事例が多発しています。
システム導入費用やライセンス料、サーバー使用料、ベンダーによるサポート費用など、継続的に発生する運用コストも含めた総合的な判断が重要です。
▼おすすめの関連記事
「企業向けeラーニングの費用対効果とは?知っておきたいポイント」
コンテンツ作成・管理の負荷が重い
質の高い教育コンテンツを継続的に提供するためには、企画から制作、運用、定期的なアップデートまでを一貫して管理する体制が欠かせません。特に自社で教材を内製する場合、専門家による監修や動画の分かりやすい編集など、高度な専門知識と技術が必要となり、担当者への負担が大きくなります。
さらに、学習者からのフィードバックを反映したコンテンツの改善や見直しも定期的に実施する必要があります。その結果、学習者の負担は軽減されても、担当者の業務負荷が大幅に増大し、他の重要業務に支障をきたす可能性があります。
一方、専門の企業にコンテンツの作成や改善を委託することも可能ですが、作成費用は高額になることが多く、外部委託コストの増大という新たな課題に直面することもあります。
デメリット③:eラーニング研修効果への影響と学習者の課題
eラーニングは学習者の自律性に大きく依存するシステムであるため、個人の学習姿勢や環境が研修効果に直接的な影響を与えます。優れたシステムやコンテンツを用意しても、必ずしも期待した学習成果が得られるとは限りません。
学習定着率・モチベーション維持の困難さ
eラーニングでは、学習者自身が自律的に学習を進める必要があります。各自のペースで学べる反面、自主的な学習姿勢に頼る場面が多く、学習の進行が遅れたり、モチベーションが低下したりすることがあります。特に、目標が曖昧だったり、学習計画が不十分な場合には、この問題が顕著に現れます。
また、一人で学習することが多いeラーニングでは、学習意欲の維持が難しい場合があります。他の学習者との競争や共同作業が少ないことが一因となり、孤立感がモチベーションを低下させてしまうのです。
さらに、eラーニングでは学習者自身がスケジュールを管理しなければいけませんが、適切な計画を立てることは容易ではありません。自己管理能力が低いと計画が曖昧になり、スキルや知識の定着が遅れることもあります。
コミュニケーション・エンゲージメントが不足する
eラーニングでは、対面の授業と比較して、同僚やクラスメートとの直接的な関わりが大幅に減少します。学習者同士や講師との双方向の交流がほとんど無くなるため、疑問点の質問や意見交換がしにくくなり、学習者がストレスや孤立感を抱くケースが増加しています。
特に、実践型スキルや現場感覚が必要な場合、リアルタイムのロールプレイやグループワークが行いづらくなります。学習を通じて築かれる人間関係や協力の機会が制限された結果、学習体験の質が低下する可能性があります。
また、社会的な交流が制限されることで、コミュニケーションスキルの発展にも影響が出るでしょう。対面でのディスカッションやグループワークを通じて培われるコミュニケーション能力が、eラーニングでは充分に養えません。
その結果、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力といった実技を伴うスキルの習得には、eラーニング単体では限界があります。チームビルディングやコミュニティ形成といった組織的な課題への対応も困難になります。
デメリット④:eラーニング特有の時間管理課題
eラーニングは学習の柔軟性を提供する一方で、学習者に高度な時間管理能力を要求します。学習者が他の業務や私的な活動に時間を割いた結果、学習時間が不足し、企業が想定していたレベルのスキルや技術が定着しないという事態も珍しくありません。
効果的な学習スケジュールを作成できない
eラーニングは自由度が高い反面、学習者自身がスケジュールを管理しなければいけませんが、適切な計画を立てることは容易ではありません。自己管理能力が低いと学習計画が曖昧になり、受講が後回しにされることでスキルや知識の定着が遅れることも少なくありません。
また、自分で学習計画や進捗管理ができない状況が続くと、研修全体の継続率や定着率の低下リスクが高まります。締切に追われるような状況での学習は効果が限定的になるため、企業側による適切なフォローとサポートが不可欠となります。
自己管理能力の育成と目的意識が結果に直結する
eラーニングにおいて、自己管理能力を育成することは非常に重要です。時間管理能力や明確な目標意識が不足している場合、自己学習の継続が困難になり、eラーニング全体の継続率や定着率に深刻な影響を与えるからです。
しかし、自己管理能力の育成は簡単には行えず、自身で培うのは非常に難しいです。そのため、会社側のサポートが十分でない場合、学習者が自己管理に苦労し、学習成果が思うように上がりません。社員の主体性に完全に依存するのではなく、自律的な学習意欲を継続的に喚起し、学習習慣を確実に身につけられるような組織的な働きかけが重要になります。
▼おすすめの関連記事
「避けては通れない!人材育成の課題とは何か?」
▼【フォーム入力はメールアドレスだけ】eラーニングの導入を検討中の方必見!▼
eラーニングのメリット・デメリットを網羅的にご紹介しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
従来型研修とeラーニングのメリット・デメリットを徹底比較
従来の集合研修とeラーニングには、それぞれ異なる特徴と課題があります。効果的な人材育成を実現するためには、それぞれのメリットとデメリットを正確に把握し、研修の目的や対象者の特性に応じて最適な学習手法を選択することが重要です。
比較項目 |
従来型研修(集合研修) |
eラーニング |
時間と場所の自由度 |
× 時間・場所に制約あり、スケジュール調整が困難 |
◎ いつでもどこでも学習可能 |
教育の質と均一性 |
△ 講師によって内容や質に差が出る |
◎ 全員に同じ教材を提供でき、教育の均質化が可能 |
学習ペース・反復学習 |
× 一斉進行型で、個人の理解度に応じた対応が難しい |
◎ 自分のペースで学習・再視聴・スキップが可能 |
相互作用・コミュニケーション |
◎ 講師や他学習者との対話、グループワークで学び合いが可能 |
△ 一方通行になりがち |
学習管理・進捗把握 |
× 出欠や理解度を手動で管理 |
◎ LMSで進捗・成績を自動記録 |
教材の更新性 |
× 修正・再配布に手間がかかり、迅速な対応が難しい |
◎ デジタル教材の修正・差し替えが簡単で、常に最新の内容を提供可能 |
モチベーション維持 |
◎ 緊張感や対面の刺激により、モチベーションを維持しやすい。 |
△ 孤立しやすく、継続意欲が下がる可能性あり |
必要な環境・知識 |
◎ 特別なIT知識は不要 |
△ パソコンやスマホ、インターネット環境、基本的なITスキルが必要 |
研修担当者の負担 |
× 会場手配・講師管理・スケジュール調整など負担が大きい |
◎ 管理がシステム化され、担当者の工数を削減できる |
eラーニング導入で陥りがちな失敗事例1:導入したものの利用率が伸びない
eラーニングを導入した企業で多い失敗は、「eラーニングを導入したが社員の利用率が思ったように伸びない」ことです。せっかくコストをかけてシステムを導入・整備しても、学習者が定着せず、研修効果も実感できないケースが多発しているのです。
利用率低迷の原因分析
eラーニングの利用率が向上しない原因として、以下の要因が考えられます。
- 内容の魅力不足
- 強制感の強い受講指示
- 受講メリットの浸透不足
- システムの使い勝手の悪さ
例えば、学習を促進するために一方的なノルマやペナルティを課すと、学習者に「やらされ感」を与え、本来の学習意欲を損なってしまいます。さらに、研修の修了や成績がキャリアアップや人事評価に結びつかない場合、学習目標が曖昧になり、積極的に学ぶ動機が生まれません。
このような無理やり利用率を押し上げようとする取り組みは、社員と企業の双方にとって良い結果をもたらすことはありません。
利用率向上のための効果的な対策
eラーニングの利用率向上には、誰もが使いやすく学びやすいシステムの構築と、学習動機を高める仕組み作りが重要です。学習者の視点に立った継続的な改善により、学習意欲を高めながら利用率を向上させることが可能です。
魅力的なeラーニングコンテンツを作る
学習者の意欲を高めるためには、テキストだけでなく動画やアニメーションを活用した視覚的に分かりやすい説明が効果的です。クイズ、シミュレーション、チャットボットなどのインタラクティブ要素を導入することで、学習者が能動的に参加できる設計を心がけましょう。
また、5分から10分程度の短い単元に分けて学ぶ「マイクロラーニング」の採用も有効です。スキマ時間でも気軽に学習できるよう設計することで、通勤時間などでも学習が可能になります。さらにバッジやポイント、ランキングなどのゲーム的要素を取り入れるゲーミフィケーションを導入することで、学習者が自ら「続けたい」と感じる魅力的なコンテンツになります。
▼おすすめの関連記事
「eラーニングでの効果的な学習スケジュールの作り方と自己管理術」
eラーニング導入目的を周知する
学習者が「何のために学ぶのか」を明確に理解できる仕組みも不可欠です。導入時のガイダンスや質疑応答を徹底的に行うことで、どのような知識やスキルが身につき、どんなメリットがあるのかを具体的に示しましょう。
さらに、修了後に業務改善や昇進、資格取得に結びついた実際の事例を共有することで、学習の実用性を実感してもらうことも効果的です。キャリアパスとeラーニングの成果を連動させ、修了実績が昇格条件などに反映される仕組みを構築すると、社員の受講意欲も大幅に向上するでしょう。
UI/UXの優れたeラーニングシステムを導入する
学習プラットフォーム自体の使いやすさも、学習意欲を左右する重要な要素です。わかりやすいナビゲーションと直感的に操作できるシンプルなインターフェースを持つ学習システムを選択しましょう。
また、サポート機能を充実させ、困った時にすぐFAQやチャットで解決できる機能も、利用率向上に有効です。さらに、進捗管理機能やリマインダー機能があることで、受講漏れを効果的に防げます。「使いたくなる設計」を徹底し、導入前には必ず実地テストやトライアルを実施しましょう。
学習成果の評価連携で効果を最大化する
学習成果が社員自身の成長や企業の人事評価と連携することで、主体的な受講率を向上させる効果があります。人事評価や資格取得と連動させ、講座修了や評価結果が昇進、昇格、給与改定、資格手当に結びつく制度を設けましょう。
また、スキルマップとの連携により、研修進捗管理とスキルの可視化を行い、自分の成長を実感できるようにすることも効果的です。学習結果が「キャリアにつながる」「会社から認められている」という実感が、継続的な学習意欲を向上させます。
▼おすすめの関連記事
「離職率低下!社員のモチベーションを高める8つの方法」
eラーニング導入で陥りがちな失敗事例2:システムトラブル頻発によるクレーム対応地獄
eラーニング導入後、接続障害やエラーの多発により、担当者が苦情や問い合わせの対応で疲弊するケースも少なくありません。システムの不具合は学習の遅延や信頼失墜にも直結するため、導入時の環境検証やサポート体制の構築が極めて重要です。
システム障害が多発する原因
eラーニングの導入後、学習システムの障害が多発する原因には、次のようなものが挙げられます。
- 事前検証不足
- ベンダーのサポート体制の不備
- ユーザー環境差への配慮不足
- セキュリティ対策の軽視
導入前に十分なテスト運用や検証が行われていないと、システムが本格稼働した際に様々な問題が表面化しやすくなります。そのため、既存環境との相性確認や負荷試験など、実際の運用環境に即したテストと検証が必要です。
また、システムを提供するベンダーのサポート体制が不十分だと、問い合わせに迅速に対応できず、担当者を含めて現場全体が混乱してしまいます。特に、システムトラブル発生時のサポート体制が整っていないと、迅速な問題解決ができず、学習効率の悪化や学習者のモチベーション低下につながります。
システム問題は自社の取り組みだけでは解決できない場合も多いため、ベンダー選択の段階から徹底した事前準備と対策を講じることが重要です。
システム問題を未然に防ぐ対策
システムトラブルによる問い合わせを最小限に抑えるためには、導入前の十分な検証や社内のデジタル環境整備などが効果的です。想定外のトラブルが発生した際に現場が混乱や疲弊に陥らないよう、しっかりとした対策を講じましょう。
eラーニング導入前の十分な検証期間とトライアルの実施
学習システムが問題なく動作することを確認するため、導入前にテスト運用を実施しましょう。少人数のグループで現場と同様の環境において全ての機能を検証し、問題がないかを確認することが、システムトラブルを回避する運用につながります。
また、テスト運用には十分な期間を設け、潜在的な問題点や操作上の課題を洗い出すことも大切です。併せて、トラブルが発生した際の対応手順をシミュレーションし、実際のサポート業務についても事前に訓練しておくことがおすすめです。
サポート体制を確認する
学習システムにトラブルが発生した場合、ベンダーにシステムの不具合を解決してもらう必要があります。そのため、導入前にベンダーのサポート体制をしっかりと確認しましょう。
具体的には、次のポイントをチェックします。
- 24時間サポート有無
- レスポンススピード
- FAQ・マニュアル充実度
特に24時間サポートの有無は重要な要素です。eラーニングは24時間利用できることが大きな強みであるため、どの時間帯でも迅速に対応してもらえるかどうかは必ず確認しておきましょう。
また、他社の導入事例など、ベンダーの実績やレビューを確認することも有効です。様々な観点から信頼できるベンダーを選定し、運用担当者の負担を軽減させましょう。
推奨環境の明確化と事前周知を行う
担当者への問い合わせの中には、システムトラブルではなく基本的な操作に関する内容も多く含まれています。こうした問い合わせは迅速に解決できるものの、頻発すると業務を圧迫するため、あらかじめ学習者に対応方法などを周知しておくことが効果的です。
例えば、受講前オリエンテーションの実施、推奨端末やOS、ブラウザの周知などを行っておくことで、学習者の自己解決能力が向上し、基本的な問い合わせを大幅に削減できます。また、必要に応じて端末の貸与やネットワーク環境整備の支援も行い、適切な学習環境を整備することも重要です。
強固なセキュリティ対策でリスクを回避する
eラーニング導入後のトラブルの中でも、特に対応が困難なのが個人情報などの漏洩事故です。機密データが漏洩すると、eラーニングの停止に加え、漏洩データの確認、損害賠償など様々な問題が連鎖的に発生します。
そこで、ベンダーのセキュリティ体制の事前確認、暗号化通信や多要素認証の導入などを徹底し、不正アクセスによる機密データ漏洩を防ぐ強固なセキュリティ体制を構築しましょう。また、万が一に備えて漏洩時の初動訓練を行い、担当者や上層部と連携して迅速に問題解決できる体制を整えておくことも重要です。
eラーニング導入で陥りがちな失敗事例3:eラーニング研修効果が見えず、コストだけが増大
eラーニング研修を導入したものの、学習成果や従業員の意識変化が把握できず、運用コストばかりが増加する失敗ケースも少なくありません。投資に見合った研修効果を確実に生み出すための対策について詳しく解説します。
学習効果が見えない原因
eラーニングの研修効果を感じられない原因には、次のようなものが挙げられます。
- 目標設定が曖昧なまま導入
- 効果指標(KGI・KPI)がない
- フィードバックと改善サイクルの不在
- 研修と業務の関連性が薄い
研修効果を感じられない原因に共通するのは、そもそも研修効果を客観的に評価する基準や制度が整備されていないことです。「何を達成したいのか」が不明確なままeラーニングを導入したり、理解度を可視化する仕組みがなかったりすることで、研修効果を把握できないという根本的な問題が発生しています。
eラーニング効果を可視化する対策
投資に見合った研修効果を得るためには、研修効果の可視化が必要不可欠です。どのように研修効果を可視化し、継続的な改善につなげていけばよいのかを解説します。
eラーニング研修目的とKPIの明確化
研修効果を可視化するためには、まず研修の目的を明確化することが重要です。そのため、KGI(企業全体の目標)とKPI(個人の受講完了率、行動変容項目など)を具体的に定義し、それに合わせたコンテンツやシステムを導入しましょう。
また、KGI(最終目標)から逆算して達成度を測るためのKPIを明確化することも効果的です。どのような人材に成長してもらいたいかなどを組織内で話し合い、できるだけ具体的に設定しましょう。
▼おすすめの関連記事
「研修の効果測定を「見える化」する4つの評価レベルと測定方法を解説!」
LMSのデータ活用と分析による効果測定
eラーニングの目的やKPIの設定が完了したら、実際に学習システムのデータを活用して研修効果を測定します。受講状況、テスト結果、回答傾向などのデータをリアルタイムで把握・分析することで、学習者の理解度を客観的に測定できます。
さらに、定期的にテストを実施することで、理解度や記憶定着レベルを継続的に測定することも重要です。テスト結果の分析は個人の評価だけでなく、研修プログラム自体の評価を知ることも可能にします。そのため、研修プログラムの課題を特定し、改善することで教育の質の向上につながります。
アンケートやヒアリングによる定期的なフィードバックの収集
eラーニングの研修効果が低い場合、提供している研修プログラムの内容に課題がある可能性があります。そこで、社内アンケートや小規模なインタビューなどを実施し、実際にeラーニングを利用している社員から研修内容のフィードバックを積極的に収集しましょう。
収集したフィードバックをもとに、研修プログラムの内容や提供方法などを改善し、より学習者の役に立つ学習システムを構築しましょう。そして、継続的にフィードバックと改善を繰り返し、eラーニングの効果を最大化することが重要です。
eラーニング研修内容と業務の連携強化
eラーニングは動画などのコンテンツによる一方向の学習システムであるため、現場で必要な技術やスキルの習得には限界があります。そこで、ケーススタディやワークショップなどを導入し、eラーニングで学んだ内容を実際の現場で再学習したり実践したりできる機会を設けましょう。
eラーニングの学習内容をアウトプットする機会があることで、確実に技術やスキルが定着し、社員の成長につながります。また、同僚や上司などと関わる機会を設けることで、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力の向上にもつながり、eラーニングによる学習効果をさらに高めることが可能です。
実際の対策例から学ぶeラーニングのデメリット克服方法
eラーニング導入で多くの企業が直面する課題は、適切な戦略と継続的な運用により克服できます。ここでは、導入前の戦略的設計から運用まで、実践的なノウハウを体系的に解説します。
eラーニング導入前に戦略的な計画を立てる
eラーニングの成功は、システムの性能や教材の質だけでは決まりません。「なぜ導入するのか」「誰に何を学ばせるのか」という根本的な目的を明確にし、計画的に進めなければ、どんなに優れたシステムも効果を発揮できません。
eラーニングシステムをより効果的に活用するためには、以下4つのステップで具体的な導入計画を作成しましょう。
- 目的と施策の一貫性を確保する:「なぜ」、「誰に」、「何を」、「どのように」提供するかのか学習目的を明確化する
- ターゲット別ニーズ分析の実施:職種や部署、年代など、学習者の特性を分析してさ、最適なカリキュラムを設計する
- 測定可能なKPI・KGIの設定:「受講率100%達成」「研修コスト30%削減」「スキル評価点数20%向上」など、具体的で測定可能な指標を設定し、関係者全員で目標を共有する
- パイロット導入による事前検証:全社展開前に限定的な部署やチームでテスト運用を行い、効果測定と課題抽出を通して、本格導入時のリスクを最小化する
この4ステップを丁寧に行いシステムを導入することが、eラーニングの成功につながります。
eラーニングシステム・ツール選定の基準とポイント
システムの利便性が低いと、学習者だけでなく運用担当者にとっても有効な効果をもたらしません。そこで、学習面と運用面の両方の視点から扱いやすいシステムを選ぶことが大切です。
学習面の利便性を重視してシステムを選定する際は、次の2つのポイントに注目し比較しましょう。
- 直感的なUI/UXであるか:学習者が迷わず操作できる画面設計であることは、学習の継続性に大きく関わる
- マルチデバイス対応と操作性:スマートフォン、タブレット、PCなど、どのようなデバイスからでも快適に学習できる環境は、効率的な学習には必要不可欠。
運用面の利便性を比較する際は、次の3つのポイントに注目しましょう。
- セキュリティと信頼性:個人情報保護の観点から、データ暗号化、アクセス制御、バックアップ体制などのセキュリティ対策が十分に施されているか
- サポート体制の充実度:特に初回導入時は、技術的な質問からコンテンツ作成支援まで、包括的なサポートが受けられる体制が整っているか
- 自社システムとの連携性:人事評価システムやスキルマップとの自動連携機能があるか
このように、学習面と運用面では比較するポイントが異なります。トライアル期間はそれぞれの視点から、システムに対する評価や意見を集めるようにしましょう。
導入後の運用とサポート体制の構築する
システムは導入してからが本番です。学習効果の向上を目指し、学習者のモチベーションや継続率を高める施策やサポート体制を構築することが大切です。
学習者のエンゲージメントを高めるサポート体制には、以下のようなものがあります。
- メンター制度の導入:メンターが定期的に学習者をサポートすることで、個別指導の不足を補い、学習者が孤立しないようにする
- オンラインサポートの充実:チャットサポートやビデオ通話を利用したアドバイスを提供し、学習者が抱える疑問や問題を迅速に解決する
- コミュニティ機能の活用:学習者同士や講師との交流を促進するオンラインコミュニティやグループワーク機能を設ける
- ゲーミフィケーション要素の導入:学習進捗に応じたバッジ付与といった、ゲーム要素を取り入れ、楽しみながら継続できる仕組みを構築する
ただし、最初から完璧なサポート体制を整えるのは困難です。そこで、実際の学習結果などを分析し、必要なサポート体制を段階的に実装して環境を整えていきましょう。
技術的な問題への対応とトラブル対処法の確立する
システムの不具合など、技術的な問題が発生した場合、学習者は何もできなくなってしまうため、その時点で学習が途切れてしまいます。また、eラーニングによる学習は、学習者自身の環境によって快適性・利便性が左右されます。
そこで、次のようなサポート体制の確立も目指しましょう。
- インフラの強化:接続環境の改善やデバイスの提供を通じて、学習者が快適に学べる環境を整える
- 学習の環境整備:社内に静かで集中しやすいスペースを確保したり、必要な学習ツールの準備を行う
- 充実したヘルプデスク・FAQ体制の構築:学習者が技術的な問題に直面した際、即座に解決できる窓口と資料の整備
- 受講環境の事前チェック機能:推奨するデバイスのスペックやインターネット環境を明確に示し、個別の学習環境をチェックできる仕組みを用意する
より快適に学習してもらうには、学習用デバイスの貸出や社内に学習スペースを設けるなど、学習者に負担をかけないような対策も必要です。eラーニングシステムの導入コストとして、こうした対策の予算もきちんと用意・確保しましょう。
効果測定と改善サイクルの実現方法
より効果的な学習を実現するためには、学習者からの声をもとに改善していくことも大切です。学習システムやサポート体制を提供して終わりにするのではなく、継続的に改善していき、より良い学習環境を整えましょう。
学習システムやサポート体制の継続的な改善には、学習効果を測定しつつPDCAサイクルに沿って改善していくことが必要です。そこで、以下のようなポイントを意識して、学習者の不満や不安を解決していきましょう。
- LMSデータの可視化と活用:受講進捗、テスト結果、学習時間などの客観的データを自動収集・分析し、研修プログラム全体の課題を見つける
- 学習者の声を反映させる:アンケートやヒアリングを通じて、学習者の満足度や改善要望などの定性情報も積極的に収集する
- 定期的なPDCAサイクルの実践:定期的に指標の達成度や課題を元にコンテンツや運営方法をアップデートする
また、ある程度は対面授業のように直接的なフィードバックをするといった対応も必要です。講師からの直接的なフィードバックをすぐに受け取ることで、学習者は学習内容の理解が深まりやすくなります。そのため、全てをeラーニング上で解決しようとするのではなく、総合的な改善案の計画・実施を行いましょう。
ハイブリッド型研修でeラーニングの短所を補完
eラーニングは利便性の高い学習システムである一方、デメリットや新しい課題の頻出に頭を悩ませる企業は少なくありません。そこで、近年ではeラーニングと対面研修を組み合わせた「ハイブリッド型研修」に注目が集まっています。ここでは、それぞれの長所を活かしながら効果的な学習を提供するハイブリッド型研修について解説します。
eラーニングと対面研修を最適に組み合わせる方法
「ハイブリッド型研修」とは、eラーニングと従来の対面研修を組み合わせた新しい学習システムです。eラーニングの柔軟性と対面授業の直接的な交流を融合することで、それぞれの利点を活かすことができ、より充実した学習体験を提供できます。
eラーニングと対面研修の使い分けには、主に次のような方法があります。
- 基礎知識習得:eラーニングでの動画講義や資料学習
- 実践スキル向上:対面でのロールプレイング、グループワーク
- 質疑応答・議論:対面での講師との双方向コミュニケーション
- 復習・定着:eラーニングでの反復学習とテスト
例えば、座学や基礎知識の伝達はeラーニングで事前学習し、ディスカッションや実践型ワークは対面研修で実施します。すると、それぞれのデメリットを克服でき、学習内容の定着やモチベーション向上といった、さらなる学習効果を生み出すことが可能です。
すべての学習段階で両方の研修を設けるのではなく、段階に応じて最適な方法がどちらかを考え使い分けることが重要です。eラーニングと対面研修を的確に活用し、より柔軟な学習環境・制度を実現しましょう。
反転学習(フリップラーニング)で定着を促す
ハイブリッド型研修のメリットの1つとして、「反転学習(フリップラーニング)」が可能であることも挙げられます。反転学習とは、インプットした知識を実践を通してアウトプットすることで、学習内容の定着を促す学習方法です。
具体的には、自宅や業務時間中にeラーニングで知識を習得し、集合研修でケーススタディや実務演習、ディスカッションに取り組みます。異なる2つの学び方を行うことで、片方だけの学習よりも効率良く学習内容を定着させられます。
また、効果的な反転学習を実現するためには、以下のようなポイントを意識してみましょう。
- 事前学習の徹底:集合研修前にeラーニングでの基礎知識習得を必須とし、理解度チェックテストで到達度を確認する
- 対面時間の有効活用:対面研修では応用的な内容や実践的なワークに集中する
- 相互作用の促進:学習者同士のディスカッションや講師との対話を増やし、より深い理解と気づきを得るようにする
- フォローアップの実施:eラーニングでの復習や追加学習を行う
反転学習は、eラーニングと対面研修を交互に行うことで学習の定着を促します。そのため、それぞれの研修内容を連携させつつ、どちらも質の高い学習を目指し継続的に改善していきましょう。
▼おすすめの関連記事
「【反転学習とは?】eラーニングで学びを深める方法」
まとめ
eラーニングは時間・場所の制約を超えた、柔軟な学習機会を提供し、教育の質を均一化できる現代には欠かせない人材育成ツールです。一方で、学習者のモチベーション維持や他者とのコミュニケーションが困難など、従来の対面研修にはなかった課題も存在します。
そこで、他社の失敗例などを踏まえて、eラーニングのデメリットを克服した学習環境の確立を目指しましょう。また、eラーニングと対面研修を組み合わせた、ハイブリッド型研修も効果的です。それぞれの学習方法を組み合わせ、学習効果を最大限活かすことで、企業はより効果的かつ効率的な人材育成を実現できるでしょう。
eラーニングの導入を成功させるためには、単にシステムを導入するだけでなく、組織全体での戦略的な取り組みと継続的な改善が不可欠です。本記事で紹介したデメリットや対策を参考に、自社に最適なeラーニング環境を構築してください。
▼おすすめの関連記事
「社内研修の効果を高めるLMS(学習管理システム)とは?機能と活用事例を紹介」
「企業のためのLMS活用術!5つのメリットを公開」
「企業の未来に直結!若手社員を成長させるための育成術」
▼【フォーム入力はメールアドレスだけ】eラーニングの導入を検討中の方必見!▼
eラーニングのメリット・デメリットを網羅的にご紹介しています。
詳しくはこちらをご覧ください。