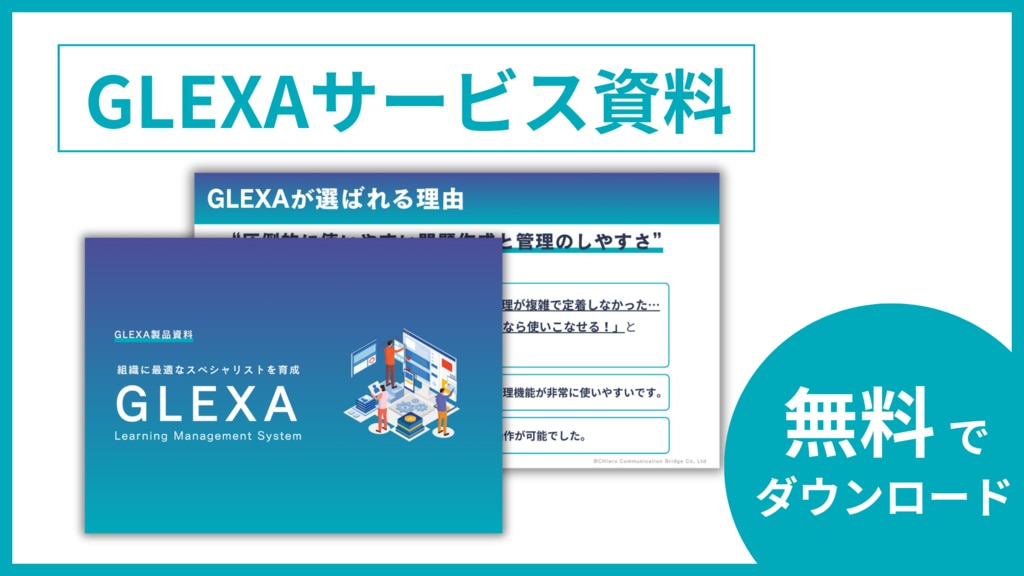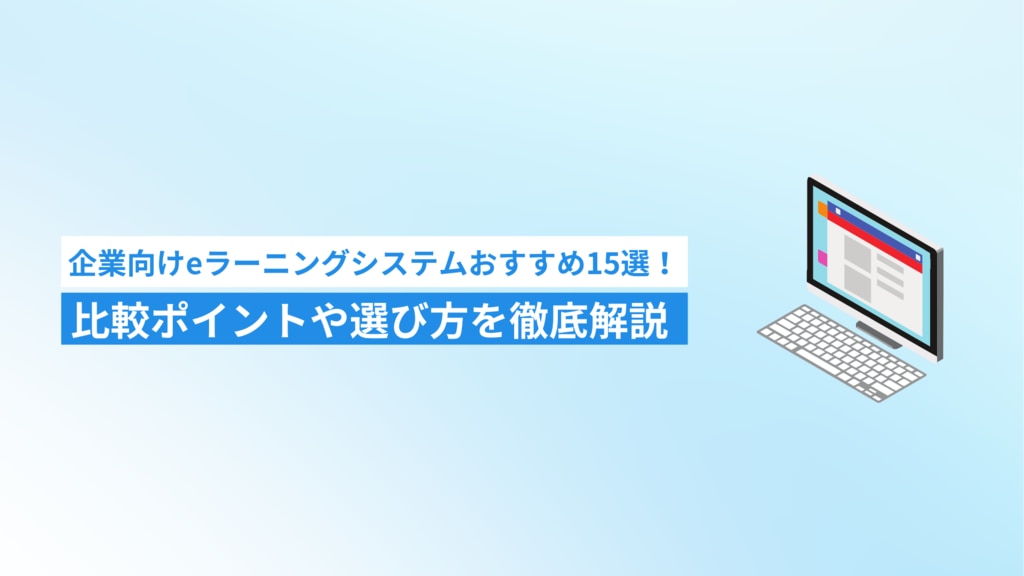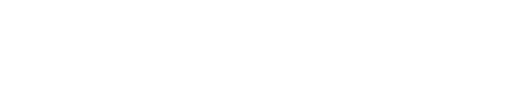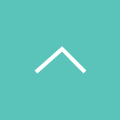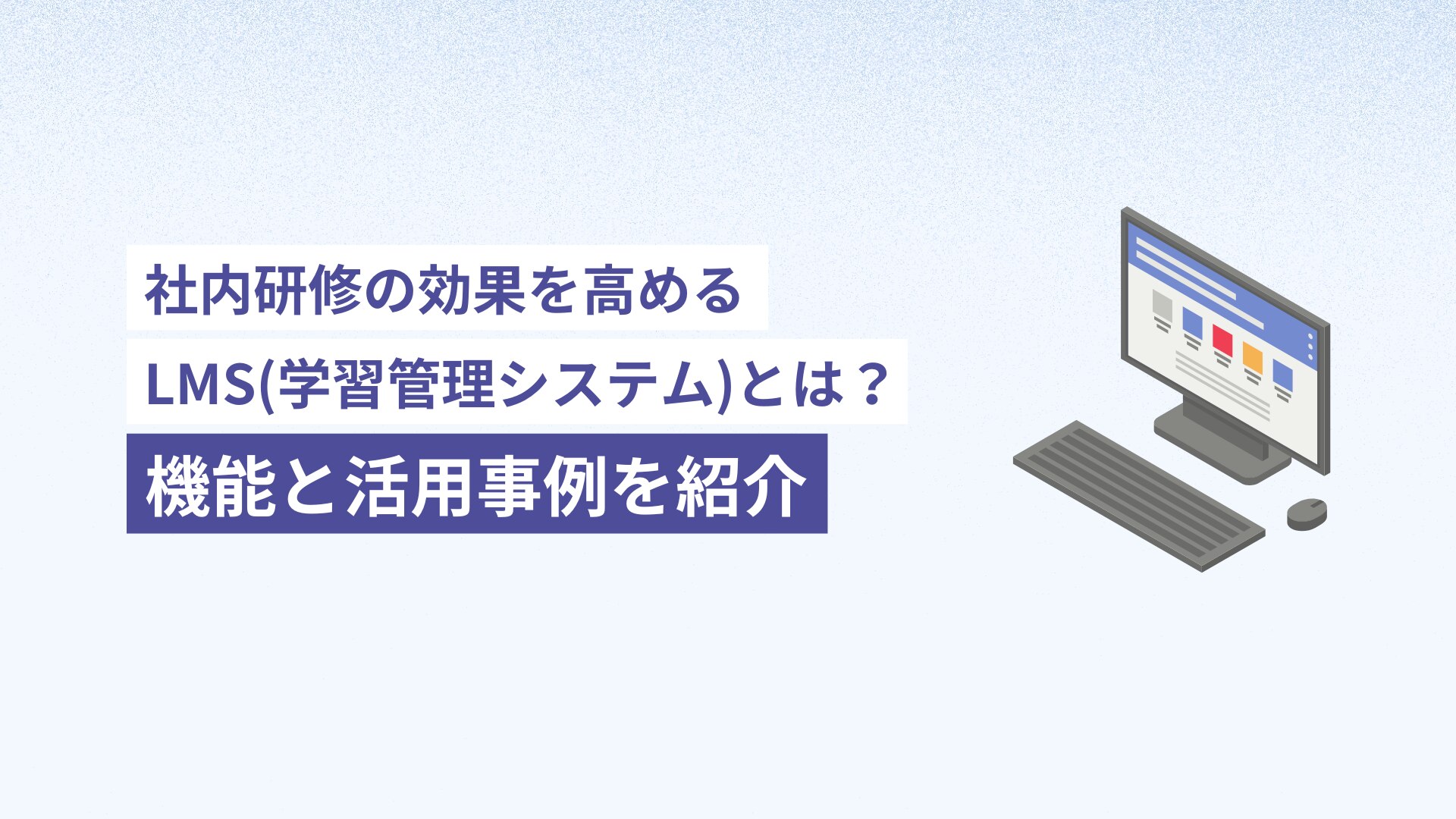
社内研修の効果を高めるLMS(学習管理システム)とは?機能と活用事例を紹介
近年、多くの企業が社内研修を効率的かつ効果的におこなうため、LMS(学習管理システム)を導入しています。
これまでの研修では、効果があまり出なかったり、業務の負担を感じたりする課題がありました。しかし、LMSを導入することで、こうした課題を解決することが可能です。
本記事では、LMSの基礎知識や機能、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。あわせて、活用事例や費用の相場、効果を最大化するポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.LMSとは
- 2.LMSの主な4つの機能
- 3.研修にLMSを導入するメリット
- 4.研修にLMSを導入するデメリット
- 5.LMSの主な活用シーン
- 6.LMSの効果を最大化する活用方法
- 7.LMSの活用事例3選
- 8.LMSの費用相場
- 9.LMS導入の流れとポイント
- 10.まとめ
LMSとは
LMSはLearning Management Systemの略称で、「学習管理システム」と呼ばれています。
パソコンやスマートフォンで研修や学習を受けられるeラーニングを、一元的に管理・運用するための基幹システムを指します。また、アンケートやテストの実施、結果の管理も可能です。
LMSは管理者が学習を管理するためのシステムと思われがちですが、実際には受講者が学びやすい環境を整えることが主な目的です。
LMSが登場した背景、eラーニングとの違い
LMSが登場した背景には、eラーニングが抱えていた非効率さや受講率のばらつきといった課題があります。
eラーニングはオンラインで教材を配布できる点で便利でしたが、学習の進捗や成果の管理が難しく、個々の受講状況が把握できない問題がありました。
また、多数のコンテンツ管理が難しい点や、受講率が上がらず効果が得られないと、運用面の課題も残っていました。
このような課題を解決するために登場したのが、LMSです。LMSを用いることで学習コンテンツの配信・管理を始め、受講者の進捗状況や結果分析を一元化できるようになりました。
結果として、担当者は受講者の習熟度が把握できるようになり、受講者側も使いやすい環境の中で学習意欲を保てるようになったのです。
つまり、eラーニングとはオンラインで学習コンテンツを配信するもので、LMSはeラーニングの管理と運用を一元化するシステムのことを指します。
▼おすすめの関連記事
「オンラインで学ぶ時代:eラーニングのメリットとデメリット」
「失敗しない!企業が選ぶべきeラーニングシステムの選び方」
LMSの種類は2つ
LMSの種類は、「オンプレミス型」と「クラウド型」の2つに分類されます。
オンプレミス型は、自社サーバーにLMSを構築して運用する方法で、セキュリティやカスタマイズ性に優れているのが特徴です。
ただし、サーバーの準備や構築にコストがかかったり、開発するのに専門知識が必要であったりします。
一方、クラウド型は、あらかじめ構築されているLMSサービスを、インターネット経由で利用する形式です。自社でサーバーを準備する必要がなく、迅速な導入やコスト削減ができます。
また、システムの保守やアップデートはサービス提供側が対応するため、運用負担を最小限に抑えられます。
自社のIT環境、セキュリティ方針、管理コストや予算の観点などから最適な方法を選びましょう。
【オンプレミス型とクラウド型比較表】
比較内容 |
オンプレミス型 |
クラウド型 |
初期費用 |
高い |
低い |
運用・保守負担 |
自社負担 |
サービス提供側が負担 |
カスタマイズ性 |
高い |
一部制限あり |
セキュリティ |
自社内のみで機密情報を
扱える
|
外部サーバーに自社情報を
預ける必要がある
|
近年のLMS機能のトレンド
近年のLMSは、AI技術の進歩により大きな進化を遂げつつあります。
特に注目されているのが、受講者一人ひとりの理解度や進行速度をリアルタイムで解析し、最適なフィードバックを自動で提供する「パーソナライズ学習」です。これにより、各々がより効率よく学習できるようになります。
その他、試験時の不正防止にもAIが活躍しています。例えば、事前に登録された受講者の顔写真と、試験開始時に撮影した画像を、AIが照合する機能などです。これに承認されると、試験が受けられます。
さらに、試験の最中でも本人確認をおこなうことが可能となり、不正を徹底に防ぐ取り組みが実現しました。
AIによる最新機能を有したLMSを導入することで、さらに効果的な人材育成が可能になるでしょう。
▼おすすめの関連記事
今時の人材はどんな感じ?人材育成のトレンド解説!
LMSの主な4つの機能
LMSには多くのベンダーが登場し、提供される機能も多様化していますが、主に以下の4つがあります。
- 受講者向け機能
- 管理者向け機能
- 教材の作成・編集・管理機能
- 教育の指導・サポート機能
各機能ごとに詳しく解説していくので、参考にしてください。
受講者向け機能
LMSの機能により、受講者は自分のペースで効果的に学べる環境を整えられます。主な機能は以下の通りです。
- 教材や動画コンテンツへのアクセス
- 学習の進捗状況や成績の確認
- 一斉テストや資格本試験の受験
- 理解度チェックテストの受験
- レポートやアンケートの提出
これらの機能によって、受講者は動画の視聴や学習、アンケートやレポート提出までをワンストップで行えるため、効率的で快適な学習環境が実現します。
さらに、疑問をすぐに質問・相談できる掲示板やチャット機能などを備えたLMSも増えています。
管理者向け機能
LMSの管理者向け機能は、受講者や研修全体を効率的に取りまとめ、質の高い教育運営をサポートします。主な機能は以下の通りです。
- 受講者の登録・出欠管理
- 受講履歴の自動集計
- 学習進捗や成績の一括把握
- アンケートやレポートの出力・管理
担当者は受講者の学習状況を把握しやすくなり、課題の抽出もスムーズに行えるため、フォローアップ施策を効率よく立てられるようになります。
さらに、研修案内やアンケートのお願い、個別リマインダーなど、メール送信が自動化できるため、担当者の業務負担を大幅に減らすことができます。
教材の作成・編集・管理機能
LMSには、学習効果を高めるための教材作成や管理機能が充実しています。
例えば、テキストや動画、クイズなど多様なスタイルでの教材を作成・編集でき、アップロードも簡単です。なかには、自社の資料を基に、オリジナル教材を作成できる機能を備えているサービスもあります。
また、教材のアップデート管理機能を備えているため、内容の更新や差し替えもスムーズです。
教育の指導・サポート機能
受講者一人ひとりの成長を促す教育の指導・サポート機能も、LMSには備わっています。
これにより、受講者ごとの学習状況や理解度の把握がしやすくなり、管理者は状況に応じた個別フィードバックや指導をすばやく提供できます。
また、受講者からの質問や相談に対応する手段として、メッセージ機能や掲示板、グループチャットなどが1つのプラットフォームに統合されているため、情報のやりとりが非常にスムーズです。
さらに、AIを活用した自動アドバイスやリマインダー機能など、学習のモチベーション維持や離脱防止に役立つ機能を備えているサービスもあります。
▼おすすめの関連記事
eラーニングシステムのアンケート機能とは?
研修にLMSを導入するメリット
LMSを導入することで、従来の集合研修では実現しにくかったさまざまなメリットが得られます。
どのようなメリットがあるのか、受講者と管理者それぞれの視点から紹介します。
受講者側のメリット
受講者がLMSを活用するメリットは、進捗状況や理解度を自分で確認できる点です。従来のeラーニングでは分からなかった自分の学習状況を見える化できるため、モチベーションを保ちやすくなります。
また、質問機能やフィードバック機能をスピーディーに活用することで、不明点がすぐに解消でき、学習を進めやすくなるのもメリットです。
さらに、一部のサービスでは、受講者同士でオンライン交流ができる機能を用意している場合もあり、意見や情報共有を通じて学習意欲の向上が期待できます。
管理者側のメリット
LMS導入により、管理者は今までの研修方法では分かりづらかった受講者の進捗状況や理解度をすぐに確認できるようになります。そのため、迅速な個別フォローがしやすくなり、より効果的な人材育成につなげることが可能になりました。
また、それぞれの得意分野と苦手分野も把握できるようになるので、最適な人員配置を考えるうえで有益な情報が得られます。
加えて、研修プログラムの作成や変更も、1つのシステム上で完結でき、資料配布や回収の手間も大幅に削減されます。
受講履歴やテスト結果などのデータが自動的に集約されるので、研修効果の分析や次回以降の改善にも役立ちます。
研修にLMSを導入するデメリット
LMSは多くのメリットを持つ一方で、導入や運用段階で以下のようなデメリットも存在します。
- コンテンツ作成に手間と時間がかかる
- 実技研修には向かない
- 学習意欲が個人に委ねられる
一つずつ詳しく解説していきます。
コンテンツ作成に手間と時間がかかる
LMS導入で研修効果を最大限に引き出すためには、高品質なコンテンツの作成が不可欠です。
既存コンテンツでは不十分な場合、新しい教材を作成しなければならず、受講者のレベルにあわせた設計や動画・資料の制作などで、準備に手間と時間がかかります。
また、一度作った教材も定期的にアップデートが必要で、継続的なリソース確保が求められます。
特に人員や時間に余裕がない企業では、こうした準備は負担に感じる部分でしょう。人手やノウハウが足りない場合は、学習コンテンツ作成に精通した外部に依頼するのも、1つの手段です。
実技研修には向かない
LMSは知識を習得する研修と相性がよい反面、体を使う必要がある実技研修やリアルタイムのコミュニケーションが求められる研修には向いていません。
例えば、機械操作や対人スキルのトレーニングは、映像や資料だけだと細かい動きや表現のニュアンスが伝わりにくく、練習には限界があります。
また、講師がその場でフィードバックや指導をする必要がある研修もLMS越しでは難しいでしょう。
こうした研修では、まずLMSで基礎知識を身に着けたうえで、実技部分を対面で行うスタイルが有効です。目的に応じて最適な学習形式を選択しましょう。
学習意欲が個人に委ねられる
LMSの研修は受講者自身による主体的な学習が基本となるため、受講者のモチベーション管理が課題になることがあります。
システム上で自身の学習状況が把握しやすい点はモチベーション向上につながりますが、対面よりも緊張感が薄れやすく、集中力を保ちにくくなる場面があります。
結果として、一部の受講者は学習が進まなかったり、途中で離脱してしまったりするケースも考えられます。
このような課題に対して、定期的なフォローやインセンティブ制度の導入、受講者同士での情報共有の場を設けるなど、学習意欲を維持・向上させるためのアイデアを取り入れることが大切です。
自社でLMSを開発する場合は受講者のモチベーションを引き出す仕掛け作りを、外部サービスを使う場合は学習意欲を上げるような機能があるかを確認しましょう。
LMSの主な活用シーン
LMSはさまざまな教育、研修の現場で活用が進んでいます。具体的な用途を知ることで、実際の導入イメージができるでしょう。
ここでは、代表的な活用例を紹介するので参考にしてください。
全社員への研修
LMSは、企業全体で統一した教育を実施する際に役立ちます。
従来の集合研修では全員が一堂に会する必要があり、スケジュール調整や会場手配に手間がかかる上、連絡や資料配布の漏れなどの事務的なミスもありました。
その点、LMSを活用すれば、時間や場所にとらわれず、各自のスケジュールにあわせて受講できます。さらに、全社員に向けた研修案内やリマインドメールを自動で一斉送信も可能です。
受講者一人ひとりの進捗や理解度を一元管理できるため、受講漏れや理解不足の早期発見につながり、研修の質と効率が大きく向上します。
▼おすすめの関連記事
「従業員のスキルアップを図るために人事がすべきこと」
新入社員への研修
新入社員研修の効率化と質の均一化を図るのにも、LMSは有効です。
例えば、業務知識や基本的なマナーなど、毎年繰り返し実施される内容をあらかじめ動画やeラーニング教材として準備しておけば、全員に同じクオリティの研修を提供できます。
また、個人ごとの進捗や理解度の把握も簡単なので、理解の浅い分野には繰り返し学習を促すなど、個別フォローもスムーズに行えます。その結果、短期間で即戦力となる人材育成が可能になります。
階層別・管理職・職種別向けの研修
LMSは、社員の階層や職種ごとに異なる研修プログラムを効率よく提供できます。
例えば、管理職向けにはリーダーシップやマネジメントスキルを高めるための内容を、若手社員向けには基礎スキル研修といったように、それぞれの立場にあわせたカリキュラムを容易に組み立てられます。
さらに、専門職には業務特化型の最新知識や法令遵守研修を、タイムリーに提供することも可能です。
LMS上で受講者やグループごとに異なる教材をスムーズに割り当てられるため、業務が効率化され、個々にあった最適な学習環境が構築しやすくなります。
自己啓発学習
LMSは「自己啓発学習」の支援にも最適なツールです。社員の興味や必要性に応じて好きなタイミングで新しい知識やスキルを習得でき、学びの幅を大きく広げられます。
社内で用意した教材だけでなく、外部の公開コンテンツとも連携できるLMSもあり、多彩な学習機会を提供できます。
また、修了証やバッジ付与などの機能が備わっていれば、受講者の目標達成意欲が高まり、社員の自主的なスキルアップが自然に推進されていくでしょう。
社員以外の関係者に向けた研修
正社員だけでなくアルバイトや契約社員、子会社、代理店に対する研修にもLMSが活用されています。
なぜなら、関係者に一貫した教育を提供できるため、企業全体としてのコンプライアンスや業務品質の底上げに役立つからです。
システム上で繰り返し学習や確認ができるLMSを用いることで、出勤日数が限られている従業員でも仕事が覚えやすいメリットがあります。
また、グループ企業やチェーン展開している企業でも、拠点や雇用形態を問わず均一な研修がおこなえるLMSが重宝されています。
さらに、顧客に対して、自社製品やサービスの理解を深めてもらったり、新商品の案内配信をしたりすることで、満足度向上に繋げることもできます。
大学など教育機関で学生向けの教材
近年では、大学や専門学校といった教育機関でもLMSの導入が進んでいます。
講義資料やオンデマンド授業の配信、オンラインテストの実施など、さまざまな場面でLMSが役立てられています。
学生の数が多い場合でも、授業の進捗や課題提出状況を管理でき、教職員の業務負担を軽減できるのが大きなメリットです。
さらに、出席状況や理解度に応じた個別指導をおこなうことで、学習意欲や学業成績の向上も期待できます。
LMSの効果を最大化する活用方法
LMSを導入するだけでは、十分な効果は得られません。本当に意味のある研修効果を得るためには、以下のポイントを意識することが大切です。
- LMSの導入目的と自社の課題を明確にする
- 運用体制の事前計画をしっかり立てる
- 効果測定を行い改善していく
それぞれ詳しく見ていきましょう。
LMSの導入目的と自社の課題を明確にする
LMSの導入を成功させるためには、「なぜ導入するのか」「どんな課題を解決したいのか」を明確にすることが重要です。
例えば、全社員の研修受講率を上げたい、知識の定着率を高めたい、教育コストを削減したいなど、企業ごとにゴールは異なります。
自社の現状や将来の人材育成のビジョンをもとに、課題と目的を具体化すれば、必要となる機能や運用体制が見えやすくなり、現場定着もスムーズに進みます。
運用体制の事前計画をしっかり立てる
LMSをスムーズに活用するには、運用体制を整える事前計画が欠かせません。
担当者の役割分担や受講者のフォロー体制、教材の作成・管理手順など、業務プロセスを具体的に決めておくことで、運用開始後の混乱や対応の遅れを防げます。
また、トラブル時のサポート体制、必要に応じてマニュアルやガイドラインの整備も重要です。
効果測定を行い改善していく
LMS導入後は、定期的な効果測定と必要に応じた改善が欠かせません。
LMSでは、受講率やテスト結果、満足度などがデータとして可視化されるので、研修の目的がどの程度達成されているかを客観的に評価することができます。
こうしたデータを活用して教材内容やフォロー体制を見直し、課題のある部分には早めに対策を講じることで、より高い研修効果が期待できます。
さらに、データによる評価だけでなく、現場の声やフィードバックを反映した改善を繰り返すことで、より使いやすいLMS運用につながります。継続的なPDCAサイクルの導入が、LMS活用の成功か失敗かを左右するポイントです。
▼おすすめの関連記事
「企業のためのLMS活用術!5つのメリットを公開」
「LMS導入で社員教育の学習効果を最大化する方法 」
「ベンダーが解説!ニッチな業界がLMSを選ぶ時の注意点」
LMSの活用事例3選
ここでは、実際にGLEXAのLMSを導入し、効果を得た事例を3つ紹介します。
これらは、社内研修の受講率向上、大学での学習促進、病院での事務労力を削減した事例です。実践的な成功事例を知ることで、自社でのLMS活用に向けたヒントが得られるでしょう。
飽きさせない工夫で社内研修の受講率100%【住友電設株式会社】
1つ目は、紙でのアナログな研修からLMSに変え、受講率が大幅に改善した事例です。
導入先 |
住友電設株式会社 |
事業内容 |
ビル・工場の内線工事、電力、情報通信、プラント・空調工事等 |
利用規模 |
270人 |
住友電設株式会社では、導入前は現場でプリント資料を使った研修を実施しており、受講状況の把握や集計作業が困難でした。
しかし、GLEXAのLMSを導入したことで、受講者ごとの細かな進捗状況が分かるようになり、フォロー体制が強化され、全社研修の受講率100%を達成しました。
LMSでは、誰がいつ、どの資料をダウンロードしたか、研修を受けている時間などが把握できます。
これにより、社員の受講率や理解度がはっきりと可視化されたため、受講の進捗が遅い社員にはリマインドを送るなど細かなサポートが可能になりました。
国際基準の学術英語習得を加速【名古屋大学】
続いては、大学でLMSを導入し、専門性の高いスキルの習得をサポートした事例です。
導入先 |
名古屋大学 |
特徴 |
ノーベル賞受賞者を輩出する研究拠点大学として知られている |
名古屋大学では、研究者や学生の国際活動を支えるため、学術英語の習得を目指しています。
しかし、学術英語は専門的なフレーズが多いので、学生の理解度向上や学習のモチベーション維持が課題でした。
そこで導入されたのが、GLEXAの「Motion」です。
このツールの特徴は、講義動画に字幕や小テストを簡単に挿入でき、たとえば動画の再生中に自動的に一時停止して、内容理解を確認する問題を出題するといった工夫が可能です。
また長時間講義を10分ごとに分割して公開したり、学生のスキルレベルに応じて英語字幕のON・OFFが自由に選べるようにしたりなど、学習しやすい環境を作っています。
実際に講義を受けた学生からは「英語で授業を受ける楽しみがわかった」との声が寄せられています。
毎年300時間以上の事務労力を削減【近畿大学病院】
最後に紹介するのは、LMS導入で大幅に業務を削減した近畿大学病院の事例です。
導入先 |
近畿大学病院 |
事業部門 |
臨床工学部 |
利用規模 |
約3,000人 |
この病院では、医療機器の使い方や操作トラブルが発生した時の対処など、学習すべきことが多岐にわたります。
しかし、患者の治療や臨床業務が最優先であるため、診療科や業務によっては忙しい時間帯が異なります。そのため、決まった時間に職員全員を集めるのが難しいという課題がありました。
GLEXAのLMS導入したことで、職員は好きなときに動画講義を受けられるようになり、わざわざ会議室へ移動する必要もなくなりました。結果として、年間300時間以上の事務労力削減につながったと報告されています。
さらに、この病院では研修だけでなく、院内感染防止の情報共有にもLMSを活用しています。約3,000人の職員が、消毒の仕方や抗生剤の使い方などを年に2回学ぶ必要がありますが、LMSを使うことで効率的に習得できる環境が整いました。
また、院内の状況にあわせたタイムリーな情報連携もスムーズにおこなえるようになり、より実践的な運用が可能になっています。
▼詳しくはこちらをご覧ください
導入事例
LMSの費用相場
LMSの費用相場は、オンプレミス型かクラウド型、どちらを選ぶかによって異なります。
それぞれの相場を知ることで、LMS導入を考える際の判断材料になるでしょう。詳しく解説するので、参考にしてください。
オンプレミス型の場合
オンプレミス型LMSは、自社サーバーにシステムを構築するため、初期費用が高額になりやすいのが特徴です。
例えば、1,000人のユーザーで利用するケースの一般的な目安としては、初期費用が数百万円、運用費用が1ヶ月当たり10万円前後です。
また、システム保守費やバージョンアップ対応も自社負担となり、総合的なランニングコストも発生します。
ただし、独自運用が可能なため、自社のニーズに沿った細かなカスタマイズができる点がメリットです。セキュリティ重視や専門的運用ニーズのある企業には適した選択肢でしょう。
クラウド型の場合
クラウド型LMSは、導入のハードルが低く、月額または年額のサブスクリプションモデルで利用するのが一般的です。
初期費用は無料〜数十万円程度で済むケースが多く、利用規模や機能によって差はありますが、月額1ユーザーあたり数百円〜数千円程度が相場です。
システム保守やアップデートはベンダー側がおこなうため、運用負担も軽減されます。コストを抑えつつ、スピーディーな導入を優先したい場合や、カスタマイズ要件が少ない企業にはクラウド型がおすすめです。
LMS導入の流れとポイント
LMSをスムーズに導入・運用するには、計画的なプロセス設計と、ベンダー選定における比較ポイントの理解が不可欠です。
ここでは、LMS導入までの具体的なステップと、失敗しないためのチェックポイントを解説します。
導入ステップ
LMS導入のステップを以下にまとめました。
- 運用目的や自社課題を明確化し、必要な機能や利用者数、予算などの要件定義を決める
- 複数のLMSベンダーから資料やデモを取り寄せて比較検討。トライアル導入があれば、操作性や運用負荷を現場で確認
- 導入決定後に環境を構築する(サイトの開設、教材作成、人事データの連携など)
- 運用準備(運用テスト、本番データ登録、マニュアル準備、説明会の実施など)
- 運用開始後は効果測定とPDCAサイクルを定着させ、必要に応じて機能追加やカリキュラムの調整をおこなう
以上のプロセスを丁寧に進めることで、現場に定着しやすく、効果の高いLMS運用が実現します。
複数ベンダーを比較するポイント
LMSのベンダーを選定する際は、以下のポイントに注目することが大切です。
- 使いやすさ
- 柔軟性
- SCORM規格対応の可否
- サポート体制
それぞれ詳しく見ていきましょう。
使いやすさ
LMS選定において、最も重視したいポイントの1つが「使いやすさ」です。
操作画面が直感的でわかりやすいかどうかは、受講者にとっての学習のしやすさと、管理者にとっての運用効率に大きく影響します。
複雑なメニューや多すぎる機能は運用を煩雑にし、LMSの定着を妨げる要因になりかねません。そのため、デモや試用期間中に、画面構成やスマートフォンやタブレットでの操作性を確認しましょう。
ITリテラシーに関係なく誰でもスムーズに利用できるLMSを選ぶことで、全社的な活用促進とストレスフリーな運用につながります。
柔軟性
LMSを導入を検討する際には、今後の自社の業務フローやニーズ変更に、どれだけ柔軟に対応できるかも重要なポイントです。
柔軟性の高いLMSであれば、権限設定やグループ分け、カリキュラムのカスタマイズ、外部システムとの連携など、自社独自の要件にあわせた運用が可能になります。
また、将来的に受講者が増えたり、新たな教育コンテンツを追加したりする可能性があっても、スムーズに対応できる設計かを確認しておきましょう。ビジネス環境や教育課題の変化に柔軟に対応できるシステムを選ぶことで、長期的なLMS運用が実現します。
SCORM規格対応の可否
LMSを選定する際には、教材管理や将来的な拡張性の観点から「SCORM規格」に対応しているかを確認しましょう。
SCORMとは、eラーニング教材やLMSの標準規格であり、この規格に準拠していれば他のLMSへ移行する場合でも、受講者の学習履歴や今までの教材が引き継がれます。また、自社独自の教材だけでなく、外部教材も柔軟に導入できる点もメリットです。
LMS導入時は、将来の運用も見据え、SCORM対応の有無を必ずチェックしましょう。
サポート体制
LMSを安定して運用するためには、ベンダーのサポート体制も重要な比較ポイントです。
とくに、導入直後は操作に不慣れなユーザーも多く、マニュアルの整備や初期設定の支援が充実しているかどうかが、現場での負担や混乱のリスクに大きく影響します。
また、万が一のトラブル発生時にも、迅速に対応してもらえるかどうかは大きな安心材料です。
加えて、定期的な機能追加やアップデート情報の提供はあるか、相談に柔軟な対応をしてくれるかなども確認しておくと安心です。
その他、24時間対応や専用サポート窓口の有無、FAQサイトの充実度も選定材料になります。
まとめ
LMSは、社内研修や人材育成を効率化し、多様な学習スタイルに対応できる仕組みで、受講者・管理者の双方にとってメリットがあります。
オンプレミス型とクラウド型、それぞれにコストや運用メリットの違いがあるため、自社の状況やニーズにあわせた選択が必要です。
また、導入する際は、自社の課題と目的を明確にし、継続的な改善を心がけることが持続的な人材育成と組織力の向上につながります。
GLEXAは、これまで300万人以上の学習をサポートしてきた実績をもとに、社内研修の効率化や研修コストの削減を実現します。また、直感的に使えるシステムと、カスタマイズの柔軟性が特徴です。
研修の質を高めたい、運用をもっと楽にしたい、そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。
以下のフォームより、【メールアドレスのみ】の情報入力で資料ダウンロードが可能です。