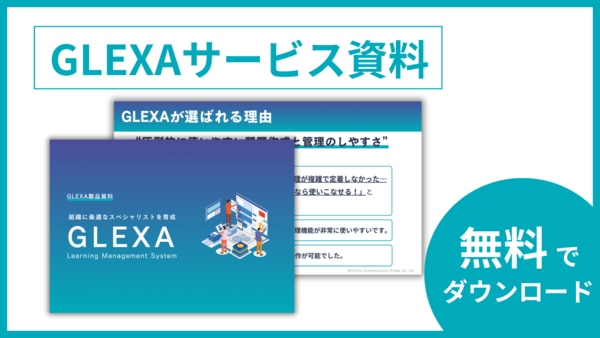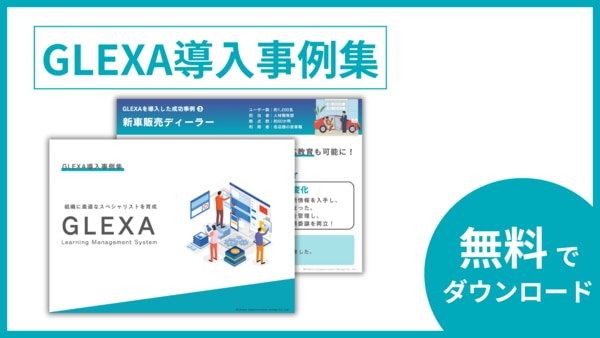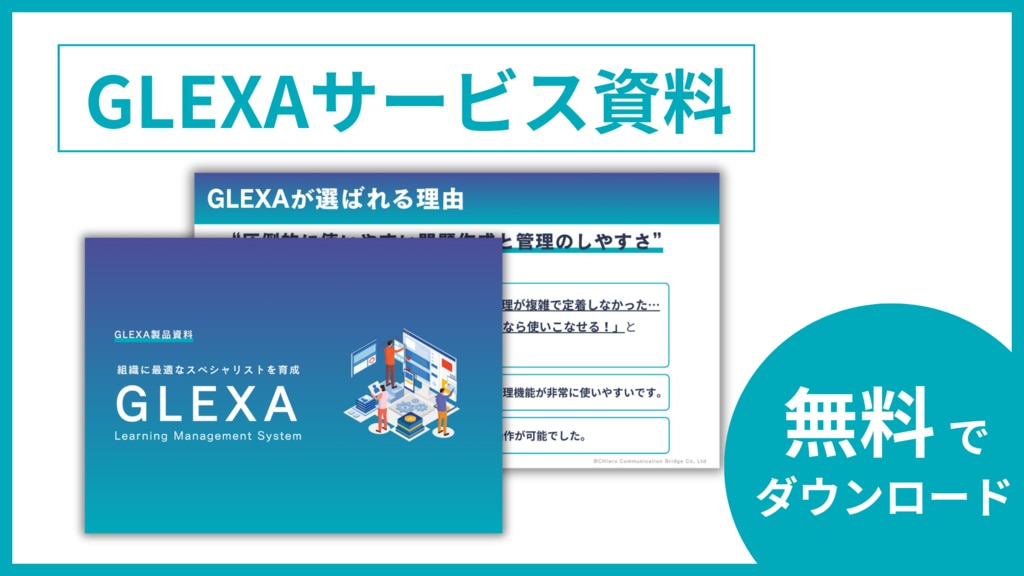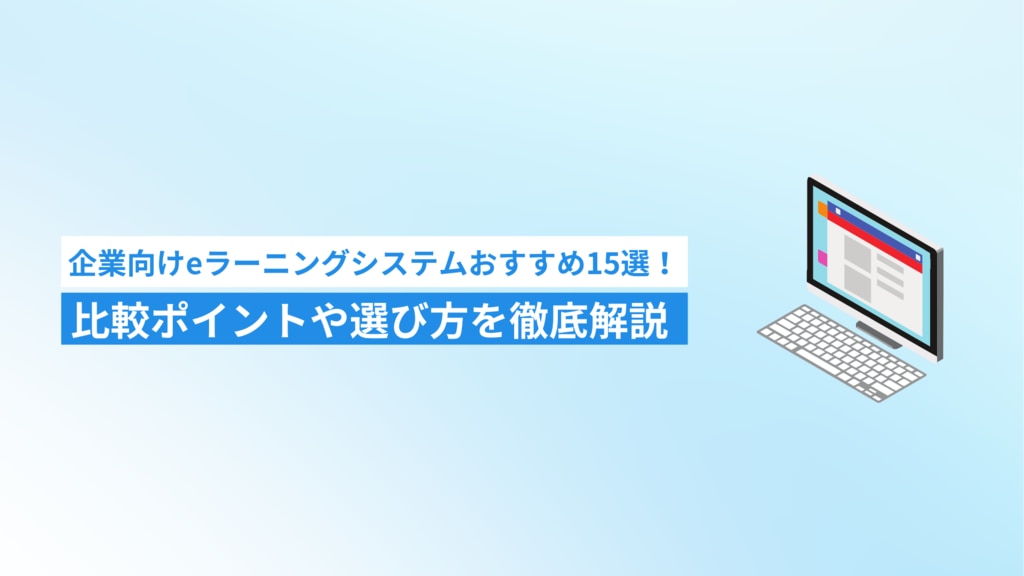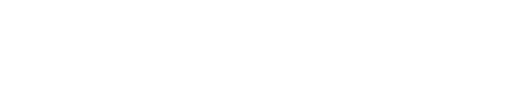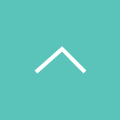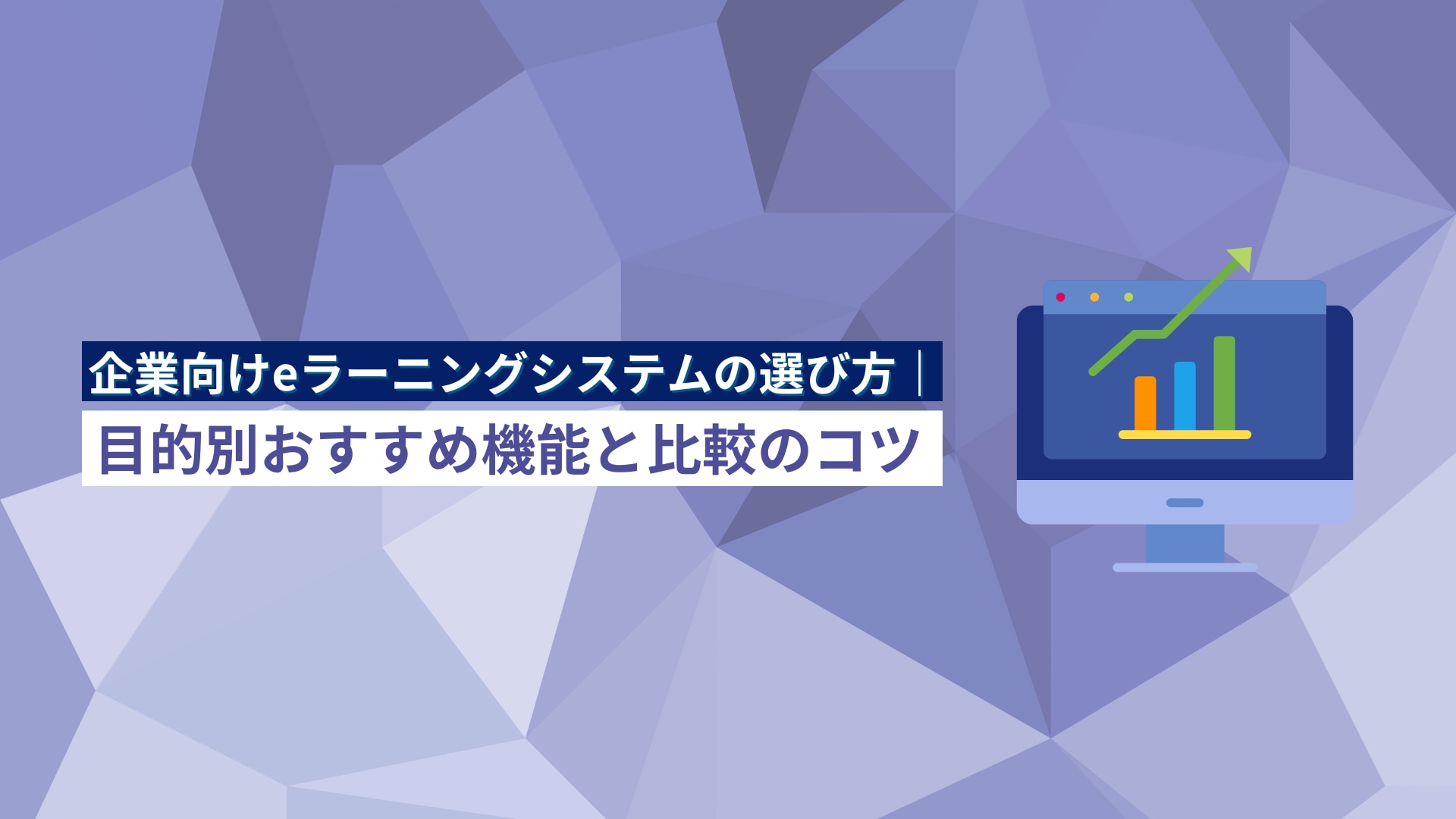
企業向けeラーニングシステムの選び方|目的別おすすめ機能と比較のコツ
eラーニングは、社内の教育課題解決のカギとなるシステムです。導入してから後悔しないよう、自社の目標や体制に合ったeラーニングの選び方について解説します。
本記事では、企業向けeラーニングシステムの失敗しない選び方、導入後の運用ポイントまで詳しく解説します。自社に最適なシステム選定にお役立てください。
目次[非表示]
eラーニングシステムの選び方|失敗しない比較ポイント
eラーニングは、社内教育の課題を解決する有効な手段です。導入後に失敗しないために、自社の目的や体制に合った最適なeラーニングシステムの選び方を解説します。
eラーニングシステムの導入目的を明確にする
eラーニングを導入するときに、最も重要なことは「何のために導入するのか」という目的の明確化です。新入社員の早期戦力化、法令遵守研修の標準化、人材育成の効率化など、導入する目的は企業によってさまざまです。そのため、導入目的をはっきりさせることで、必要な機能やシステムを絞り込むことができ、最適な選定が可能になります。
導入目的が曖昧なまま進めると、不要な機能にコストをかけたり、必要機能が不足したりするなど、さまざまな問題が生じます。導入効果を実感することも難しくなるので、eラーニングの導入に失敗したと感じることもあるでしょう。
自社の課題に合わせた機能を比較する
eラーニングには、教材作成や配信から、進捗管理、評価・テスト、コミュニケーション支援、多言語対応など、さまざまな機能があります。だからこそ、自社が最も課題としているポイントにあわせて、最適な機能を備えているかを比較しましょう。
多機能なシステムほどよいと判断しがちですが、機能が多いからといって優れているとは限りません。むしろ、使わない機能が出てしまい、システムを持て余してしまうことも多いです。そのため、自社の現場の利用しやすさや運用形態に合った機能かどうかを比較し選定することが、eラーニング導入の成功の鍵となります。
セキュリティとデータ管理体制を確認する
eラーニングは、社員の個人情報や学習履歴、評価データなど機密性の高い情報を扱います。そのため、情報漏えいや不正アクセスのリスクを抑えるため、システムのセキュリティ対策は非常に重要な比較ポイントです。
具体的には、次のような対策を講じているかを比較します。
- 通信の暗号化(SSL/TLS)
- アクセス権限の厳格管理
- 多要素認証の導入
- 定期的な脆弱性検査や監査の実施
- ISMS認証、プライバシーマークの取得
クラウドサービスの場合は、データセンターの所在地が国内であるかも重要です。大切なデータをきちんと守れる、信頼できるeラーニングを選択しましょう。
費用対効果と料金プランの内訳を比較・分析する
eラーニングの導入・運用にかかる費用は、主に次のようなものです。
- システム利用料(初期費用、月額費用、ユーザー数課金)
- コンテンツ作成費
- 保守・サポート費
- カスタマイズ費用
特に、1IDあたりの利用料で表示されている場合、一見安価に見えても、結果的に割高になるケースもあるため注意が必要です。機能のカスタマイズや学習コンテンツの拡充などによって、オプション費用が加算されるケースも少なくありません。
そのため、長期的な費用対効果を見極め、それぞれのシステムの価格比較をすることが重要です。ベンダーから見積もりを得た場合は、内訳をしっかり確認し、自社の利用規模や目標と予算にきちんと適合するかをチェックしましょう。
サポート体制と実績をチェックする
eラーニング導入後は、問い合わせやトラブルが頻発します。そのため、ベンダーの運用サポートは、eラーニングのスムーズな導入には必要不可欠です。サポートの種類(電話・メール・チャットの対応時間)、対応品質、操作研修の有無などをしっかり調査しましょう。
トラブル発生時の解決スピードや、過去の導入実績もチェックしておきたいポイントです。特に、同業種や同規模の企業実績が豊富だと、自社特有のトラブルにも迅速に対応してくれるため、より信頼してサポートを任せられます。そのため、導入実績や成功事例なども、きちんと確認しておきましょう。
既存システムとの連携性を確認する
eラーニングの運用効率を上げるには、人事評価システムや勤怠管理システム、社員データベースとの連携が必須となる場合が多いです。そのため、導入候補のシステムがCSV出力やAPI連携などで、既存の社内システムとスムーズに情報連携できるかどうかも確認しておきましょう。
連携機能が不足していると、受講履歴や成果を手動で入力・管理する負担が増大し、運用効率やデータの整合性にも悪影響が出ます。長期的なDX推進を目指すためにも、eラーニングの柔軟性・連携性能も細かく調べましょう。
▼おすすめの関連記事
「コストと効果を最大化!eラーニングシステム選定のポイント」
「こんなeラーニングシステムに要注意!導入時見逃せないポイント」
【メールアドレスのみ】の情報入力で資料ダウンロードが可能です。
スムーズにeラーニングを社内展開させるステップ
eラーニングの社内展開を成功させるには、ただシステムを導入するだけでは不十分です。漠然と導入した企業には、狙い通りの学習効果が出ず、コストを無駄にしたと感じる企業もあります。そこで、スムーズかつ効果的にeラーニングを社内展開するための方法を解説します。
企画・検討
eラーニング導入の最初のステップは、導入目的と効果指標(KPI)を明確に設定し、関係者間で共有することです。導入の成否はこのステップで決まるといっても過言ではないため、時間をかけてでも、しっかり企画・検討を行いましょう。
人事・教育担当者、現場マネージャー、IT部門といった、各部門の関係者との意見交換も重要です。各部門の課題や要望を出し合い整理して、全社的な合意形成を図ることで、必要な機能などが具体的に決まります。
学習者の特性(年齢層、ITリテラシー、業務の繁忙度)や業務スケジュールも考慮して、現実的な導入計画を立案しましょう。念入りに詳細な計画を立てることが、スムーズなeラーニング導入に欠かせません。
選定・準備
次のステップは、定めた要件をもとに、実際に社内に導入するeラーニングの選定です。必ず複数のシステムを比較し、定めた導入目的や解決すべき課題に合わせた最適なeラーニングを見つけましょう。
なお、選定では以下のポイントに注目しましょう。
- ユーザビリティ(使いやすさ)
- 対応端末・ブラウザ
- 学習進捗管理機能の充実度
- 自動通知・リマインダー機能
- 学習データの分析機能
- セキュリティ対策
- サポート体制の手厚さ
また、既存の研修資料のデジタル化や新規コンテンツの企画・制作を並行して進めることも重要です。特に、この段階で学習コンテンツを外注するのか内製するかを決めておくと、eラーニングにかける予算管理がスムーズに進みます。
▼おすすめの関連記事
「eラーニングの基本から応用まで:コースの作り方」
導入・展開
システム導入後は、学習対象者への説明会を実施し、eラーニング導入の背景や期待される効果、具体的な利用方法を丁寧に説明します。同時に初期研修を行い、学習者が1人でも学習できる環境を整えることが大切です。
導入初期は基本操作の確認やトラブルなど、問い合わせが集中します。こうした事態に備え、社内やベンダーの問い合わせ窓口を周知し、フォローアップ体制を充実させることも重要です。
また、管理者は導入初期から受講状況を注意深く監視し、受講が滞っている社員には速やかにフォローアップを実施しましょう。きめ細やかな対応を行うことで、学習意欲の維持や定着を促すことができます。
▼おすすめの関連記事
「リソース不足でもできる!企業の人材育成戦略」
利用促進
eラーニングの受講率は、徐々に落ちていく傾向があります。そこで、高い受講率を維持するために、学習進捗の見える化と適切なリマインダー配信を行いましょう。見られているという意識が課題のやり忘れ防止となり、リマインダー通知でeラーニングの利用を促します。
また、eラーニングの結果を人事評価に反映させたり、社内ランキングなどでインセンティブを与えるなどの取り組みも利用促進に効果的です。さまざまな工夫を凝らして、学習者のモチベーションを向上させましょう。
効果測定・改善
eラーニングの効果を最大化するには、導入後の効果測定と改善活動が欠かせません。学習効果の測定では、主に次のポイントやデータに注目して分析しましょう。
- 受講率・完了率の推移
- 学習進捗状況の分析
- 理解度テスト結果の傾向
- 離脱ポイントの特定
- 学習時間と成果の相関分析
また、学習者からのアンケートや担当者へのヒアリングを通して、現状の課題を把握することも重要です。得られたデータや課題をもとに、学習コンテンツの質向上や機能の最適化を継続的に行うことで、より効果の高いeラーニングの構築に近づいていきます。
eラーニング導入後につまずきがちな課題とその対策
eラーニングを導入したものの、思わぬ課題に直面し、導入を後悔している企業も少なくありません。ここでは、多くの企業が直面する課題と原因、その効果的な解決策について解説します。
受講率が上がらない原因と解決策
eラーニング導入後、多くの企業が抱える課題の1つが、受講率の伸び悩みです。受講率が上がらない主な原因には、次のようなことが考えられます。
- 学習目的の共有不足
- 強制的な受講感による反発
- 進捗管理体制の不備
- 業務の忙しさによる後回し
これらの課題・原因の効果的な解決策には、以下の3つのアプローチが有効です。
- 目的とメリットの全社周知:導入背景と期待効果の説明、個人のキャリア向上との関連性を共有する
- 進捗状況の可視化とフォロー体制:リアルタイムで進捗を確認し、未受講者・遅延者への自動通知設定、現場管理職による定期的な声かけを実施する
- 学習環境の整備:就業時間内での受講時間確保、集中できる学習スペースの提供などを行う
- 自社で起きている原因と対策と照らし合わせて、受講率を向上させましょう。
eラーニングツールで進捗・成果を可視化する方法と活用法
eラーニングでは、学習者の受講状況を自動で収集・分析し可視化してくれます。しかし、可視化されたデータが多すぎるため、全てを上手く活用できず、ただ確認するだけにとどまっている企業も少なくありません。
eラーニングで可視化できるデータには、次のようなものがあります。
- 受講履歴の詳細分析
- テスト結果の統計的評価
- 学習時間と成果の相関分析
- 部門別・職種別の学習進捗
これらのデータは、学習の中でつまづきやすいところや苦手なところの判断に活用できます。データをもとに個別教材の推薦やフォローアップを行なって、学習効果を高めましょう。
▼おすすめの関連記事
「研修の効果測定を「見える化」する4つの評価レベルと測定方法を解説!」
管理職・現場を巻き込んで社内展開する
管理職やリーダーが積極的に参画すると、トップダウンでの学習促進効果が期待でき、企業全体の学習文化の変革につながります。なかなかeラーニングが定着しないときは、管理職やリーダーを巻き込んだ社内展開に取り組みましょう。
たとえば、学習データをもとに部下のフォローや悩み相談を積極的に行うことで、学習の定着と業務への応用が進み、社内の活性化が期待できます。eラーニングで学んだことの成功体験の共有は、他の社員にもポジティブな影響を与え、学習へのモチベーションにつながります。
自動通知・リマインダー機能を活用する
受講率や学習コンテンツ未達成の課題には、学習の自動通知や期限のリマインダー機能を活用しましょう。たとえば、受講期限の7日前、3日前、1日前といった段階的リマインダーや、未受講者への自動督促メールを行うことで、学習を促します。
ただし、通知頻度が多かったり、強制力のあるメッセージだと学習モチベーションの低下につながるリスクがあります。学習進捗に対するポジティブなメッセージを配信することで、モチベーションを向上させることも大切です。
法人向けeラーニングシステムの最新トレンド
法人向けeラーニングでは、最先端の技術に対応した、学習コンテンツや機能の更新にも力を入れています。法人向けeラーニングの2025年現在の最新トレンドについて解説します。
AI搭載や生成AI応用サービスが増加
近年、多くのeラーニングに搭載されているのがAI技術です。AIが学習状況を分析し、それに合わせて最適な学習プランを提供することで、より効果的な学習が可能となります。特に、苦手分野の補強や教材推薦、個別フォローなど、従来では難しかった個々への対応をAIが行うケースが増えています。
さらに、生成AIを使った自動教材作成や質疑応答支援も進歩しており、受講者がより効率的に学べる環境が整っています。その結果、従来のeラーニングよりも人的リソースを抑えながら、高度でパーソナルな教育体験が可能になっています。
オンライン×集合研修のハイブリッド教育やパーソナライズ学習の流行
eラーニングは利便性が高い一方、オンライン学習だからこそ学べないこともあります。そこで、従来の集合研修とeラーニングを組み合わせた「ハイブリッド型学習」が、近年急速に拡大しています。オンラインで基礎知識を習得し、集合研修でディスカッションや実践演習を行うことで、学習内容の定着率や生産性の向上が見込まれています。
また、一人ひとりのスキルや理解度に応じた「パーソナライズ学習」も主流化しています。学習者は、自分に最も適した教材で学べるため、学習のつまずきがなく、着実なスキルアップが目指せます。管理側も多様な学習スタイルを柔軟に支援することができ、結果的に組織全体の学習効果の向上を実現しています。
セキュリティ教育・DX分野のコンテンツが充実
情報漏えいやサイバー攻撃リスクの高まりを受け、法人向けeラーニングではセキュリティ教育コンテンツの拡充が進んでいます。特に、eラーニングは更新が簡単なことから、最新の脅威や法規制に対応したコンテンツが頻繁に配信されています。
また、デジタルスキルを向上させるDX教育も広がっており、ITリテラシーやツールの操作、データ活用能力の習得を支援するサービスも増えています。こうしたデジタル社会に対応した研修は、組織競争力強化に直結するため、企業が持続的な成長を図るためには欠かせない要素となっています。
VR/ARの導入で体験型学習を実現
より実践的な学習コンテンツとして、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術を活用した、体験型eラーニングが注目を集めています。没入感の高い仮想空間でのシミュレーションや実践訓練によって、現場に近いリアルな環境での状況学習が可能となりました。
特に、危険の伴う機器の取扱や安全教育などの場面では、VR技術を活用した体験型学習が非常に効果的です。座学中心の研修では難しかった「体験からの学び」をオンラインで提供できるようになったことで、実践的なスキルの習得を可能にしています。
eラーニングの導入コストを削減・節約するポイント
eラーニングの導入には、初期費用や月額のサービス料など、さまざまなコストがかかります。eラーニングは長期的に行うもののため、導入コストを削減・節約する方法について解説します。
初期費用・月額費用をきちんと把握する
基本的に、eラーニングの初期費用はシステムのセットアップ代や設備費用、月額費用(サブスク費用)にはライセンス料や教材コンテンツの利用料などが含まれています。
eラーニングの導入費用は、主に次の要素で決まります。
- システムのタイプ(オンプレミス型/クラウド型)
- 利用規模(契約人数)
- 機能の多さ
たとえば、オンプレミス型とクラウド型ではオンプレミス型のほうが初期費用が高額になり、契約人数が多くなるほど1人あたりの月額費用は安くなります。そのため、どのような規模でどのシステム・機能を導入するかを具体的に考えることが、コスト削減につながります。
さらに、カスタマイズ費用やサポート料金が追加され、後から予算オーバーしてしまうケースもあります。見積もりの際には費用の内訳を細かく確認し、隠れたコストがないか注意しましょう。
コストパフォーマンスの高いeラーニングシステムを見つける
eラーニングの導入コストを抑えるためには、必要な機能と価格のバランスを見極め、自社のニーズに合ったシステムを選ぶことが重要です。多機能であるほど高額になりやすく、使いこなせない機能が多いとコスト効率が悪くなります。
たとえば、eラーニング単体を導入して教材は自社で内製する方法や、使い放題の教材サービスを活用しつつ一部を自主作成することで、費用を抑えることが可能です。
利用人数が多い場合は、ボリュームディスカウントが適用されるシステムを選びましょう。1人あたりの単価を下げられるため、通常よりも割安なコストで利用できます。
補助金・助成金制度を活用する
eラーニングを導入する場合、国や自治体が提供する補助金・助成金制度を活用できるケースがあります。「人材開発支援助成金」や「IT導入補助金」などを利用し、費用の一部を補助してもらうことで、コストを抑えた導入が可能です。
ただし、申請には計画書の作成や各種要件の遵守が求められます。専門のコンサルタントやベンダーのサポートを受けることで、補助金・助成金制度の申請が通りやすくなります。制度は年度や地域ごとに異なるため、導入前に制度の最新情報を入手し、利用可能な補助制度を漏れなくチェックしましょう。
利用シーン別おすすめeラーニング活用事例
eラーニングの導入を考えていても、どのように活用すればよいのか分からない方も多いでしょう。ここでは、代表的なeラーニングの活用事例を紹介します。
階層別研修(管理職・若手社員・中堅層)
eラーニングは、社員の経験やレベルに合わせて学習コンテンツを配信できます。新入社員から管理職までの各階層に必要な研修を網羅的に提供し、従業員のスキルアップやリーダー育成に活用されています。特に、管理職は日々の業務が忙しいこともあり、自宅で手軽に学べるeラーニングでの学習に利便性の高さを感じる企業も多いです。
若手社員には基礎スキル習得やビジネスマナー講座を中心に提供し、継続的な能力向上をサポートします。中堅層には、専門スキルや部門間連携力向上を目的としたコンテンツが有効です。各階層で課題や成長目標が異なるため、それぞれに最適化した学習コンテンツを提供することで、効率良くスキルアップを促します。
▼おすすめの関連記事
「人材育成で大切なこと:社員のポテンシャルを引き出す重要ポイント」
業種別の具体的な活用法
eラーニングは配信するコンテンツに制限がないため、自社の業界に合わせたコンテンツで専門性の強化に役立てている企業もあります。たとえば、製造業では安全研修や設備操作を学習させることで、現場で安全に作業ができるようにサポートしています。
IT業界では、プログラミングやセキュリティ教育を中心に、常に最新技術を学べるコンテンツを揃えることで、スキルや知識の向上を促進しています。業務に必要な資格取得に向けた学習をeラーニングで行うことで、個人と企業の両方が成長可能です。
▼おすすめの関連記事
「IT企業としての危機感、DX全社教育への難しさ」
拠点間・リモート勤務における活用事例
全国に拠点がある企業やテレワークの多い組織では、eラーニングが積極的に利用されています。eラーニングは、どの社員に対しても一斉かつ均一な教育機会を提供できるため、タイムラグなく、最新情報を共有することが可能です。
さらに、社員の学習進捗を集中管理することで、各地の習熟度差を早期に把握し、フォローアップできる体制づくりにも役立ちます。都市部の支店だけ業績がよいといった偏りを是正できるため、グループ全体の成長や業績アップに効果的です。
新入社員研修やOJTの代替
新入社員は、まだ基本的な知識が身についていないため、研修内容によっては間違った知識を身につけてしまう恐れがあります。その点、研修内容が均一なeラーニングであれば、その企業に必要な知識を正確に身につけてもらうこと可能です。
従来のOJTでは、担当者の時間確保が難しい、教育の質にばらつきが出るなどの課題がありました。しかし、eラーニングで事前学習を行うことで、OJT担当者の負担を軽減し、実践的なOJTに集中できるようになります。進捗管理や理解度チェックを通じて、的確なフォローもできるため、新入社員の早期離職を防ぎ即戦力育成を加速させます。
▼おすすめの関連記事
「企業の未来に直結!若手社員を成長させるための育成術」
【メールアドレスのみ】の情報入力で資料ダウンロードが可能です。
無料トライアル・デモ体験でおすすめシステムを比較!
eラーニングは、長期的に使用するシステムのため、無料トライアルやデモ体験で使用感を把握することは非常に重要です。無料トライアルやデモ体験中のチェックポイントなどについて解説します。
トライアル期間中にチェックすべきポイント
トライアル期間中は、まず機能性や操作感、コンテンツの充実度を重点的に確認しましょう。自社の導入目的と課題解決に必要な機能が備わっているか、その機能がスムーズに利用できるかを検証します。
自社でコンテンツを作成する場合は、学習コンテンツやテストの作成しやすさ、配信機能も試すようにしましょう。実際に導入したという想定で各機能を使用し、システムの強みや弱みをきちんと把握することが大切です。
eラーニング機能の使いやすさを検証する
eラーニングは、機能の使いやすさも重要なポイントです。簡便な操作で利用できるか、学習コンテンツまでのナビゲーションが分かりやすいかなども確認しましょう。
eラーニングは1人で利用することが多いため、IT知識が低い社員でも簡単に操作できるかをチェックすることが大切です。パソコンだけでなく、スマホやタブレットからもストレスなく利用できるかを必ずテストしましょう。
操作性とUI/UXの評価方法
eラーニングの操作性を比較・評価するときは、UI/UXを中心に行います。UI/UXはeラーニングの使いやすさに直結し、学習意欲にも影響を与えます。学習コンテンツの見やすさやボタンの配置、利用フローの自然さを客観的に評価しましょう。
年齢などが異なる複数の社員に操作してもらい、アンケートや意見収集を行うと、より効果的な評価が可能です。どのようなUI/UXなら使いやすいシステムになるのかも考えておくと、カスタマイズや設計を依頼するときに役立ちます。実際の操作を通して、理想となるeラーニングを計画しましょう。
サポート体制の質を見極める
eラーニングは、運用中に問題が発生した際のベンダーのサポート体制が非常に重要です。無料トライアルやデモ体験中も、問い合わせへの対応速度や具体性、24時間対応の有無をチェックし、信頼できるベンダーかを見極めます。
導入時研修や操作マニュアルの充実度なども、重要な比較ポイントです。これらが充実していると、導入がスムーズに進み、社内での問い合わせ対応が簡単になります。eラーニングの社内展開が手軽になるので、問い合わせなどを通して細かく確認しておきましょう。
さらに、障害発生時の対応体制や、カスタマーサクセス担当の有無なども確認しておきましょう。ベンダーは長期的に付き合っていくパートナーとなるため、気になるポイントは全て確認し信頼できるベンダーを見つけましょう。
まとめ
企業向けeラーニングは、従来の集合研修の課題を解決し、効率的で効果的な人材育成を実現する強力なツールです。コスト削減、時間・場所の制約からの解放、学習進捗の可視化、教育品質の標準化など多くのメリットを提供してくれます。近年では、最新のAI技術やVR/AR、ハイブリッド学習の活用により、さらに高度な学習体験が可能になり、企業の人材育成には欠かせない存在となっています。
一方で、せっかく導入したにも関わらず、システムを使いこなせず「失敗だった」と思う企業も少なくありません。そのため、導入目的の明確化、自社のニーズに合ったシステム選定、計画的に社内へ展開することが重要です。
最適なサービスは企業の目的や状況によって異なります。無料トライアルを積極的に活用し、実際の操作感やサポート体制を確認した上で、長期的な視点から投資対効果の高いシステムを選定しましょう。
eラーニングの導入は一時的な取り組みではなく、継続的な改善とアップデートが必要な長期プロジェクトです。組織全体の学習文化醸成と、従業員の成長を支援する戦略的な人材育成基盤として、ぜひeラーニングシステムの導入をご検討ください。
▼おすすめの関連記事
「LMSの導入事例3選|導入前の課題や導入後の効果を紹介」
「企業のためのLMS活用術!5つのメリットを公開」
「LMS費用を徹底解説!導入前に知っておくべきポイントとは」
組織に最適なeラーニングシステムをお探しの方は、GLEXAをご検討ください。
GLEXAは教材の作成や配布、採点、学習者の管理など研修に必要な機能が揃った学習管理システムですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【メールアドレスのみ】の情報入力で資料ダウンロードが可能です。